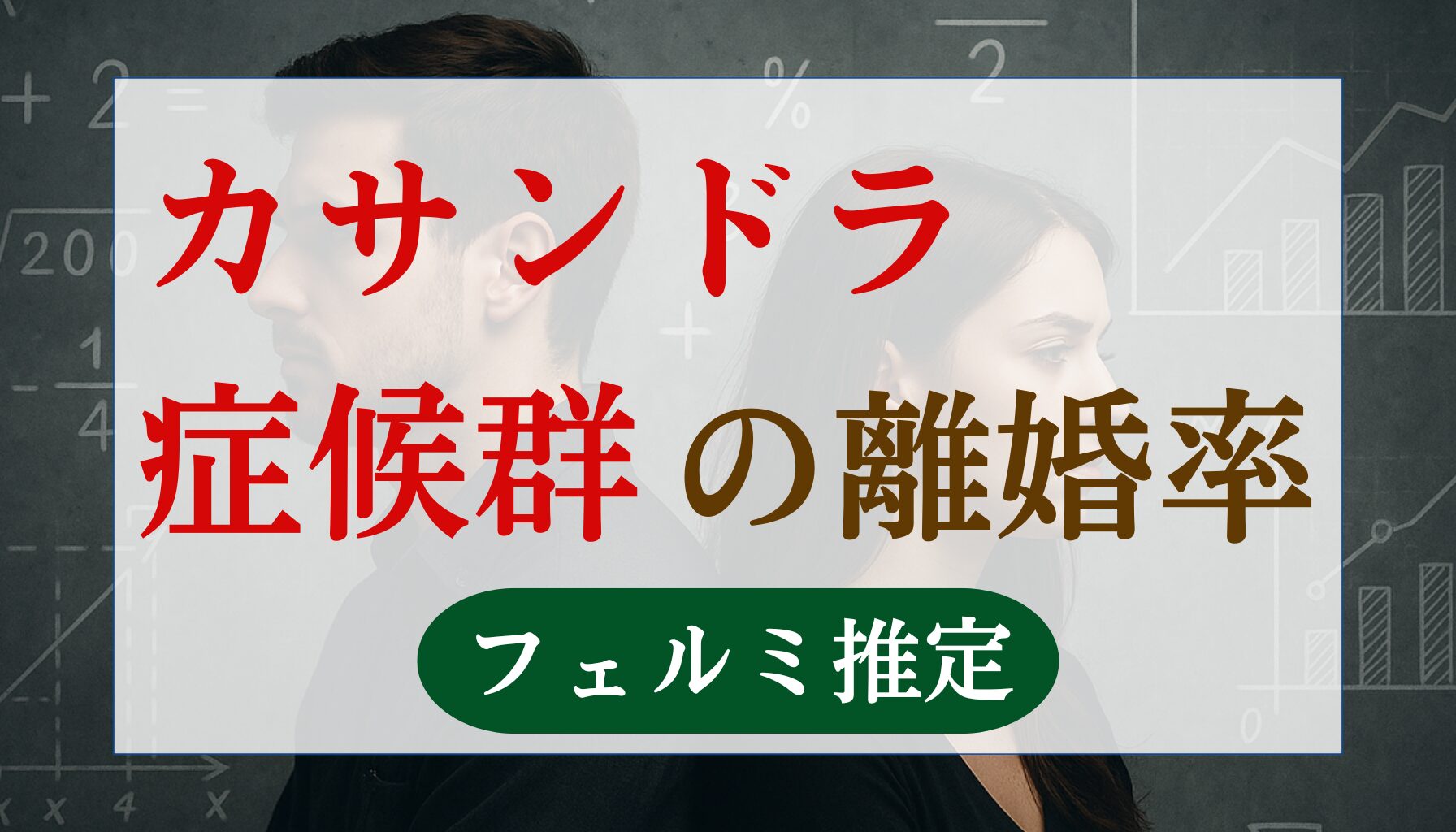カサンドラ家庭の離婚率、実は0.0239/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約1.63%。年離婚確率で見ると、なんと全国平均の約10.4倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
カサンドラ症候群の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①カサンドラ症候群とは?対象となる夫婦の定義
カサンドラ症候群とは、ASD(自閉スペクトラム症)傾向のある配偶者との意思疎通がうまくいかず、孤独や共感疲れに苦しむ状態をいいます。
今回の推定では、以下のような夫婦を対象にしています。
- 配偶者にASD傾向(診断済みでなくても可)があること
- もう一方がカサンドラ的なストレスを訴えていること
②ASD配偶者を持つ家庭の割合はどのくらい?
厚生労働省「国民生活基礎調査(2023年)」によれば、現在、日本には2,735万組の既婚カップルがいます。
この中で、カサンドラ症候群のような状況にある夫婦はどれくらいでしょうか?
以下の3つのデータを組み合わせて推定してみます。
- ASDの成人割合は約1.5%(出典:発達障害白書2020)
- そのうち結婚している割合は約15%(出典:PubMed, PMID:12638767)
- ASD配偶者のうち「カサンドラ的状況」にある割合は約70%(出典:浜松医科大学 精神科2020)
この3つを掛け合わせると、
1.5% × 15% × 70% ≒ 0.158%
これを既婚カップル数にかけると、
2,735万組 × 0.158% ≒ 約43,000組
つまり、日本国内にはおよそ43,000組の「カサンドラ的ストレスを抱えた夫婦」がいると推定されます。
③仮定と統計から推定した年間離婚確率・件数は?
浜松医科大学の調査(2020)によると、カサンドラ症候群に該当する夫婦の「5年以内の離婚率」は28%とされています。
これを1年あたりの確率に直すと、
年離婚確率 ≒ 1 − (1 − 0.28)^(1/5)
≒ 1 − 0.945 ≒ 約0.055(≒5.5%/年)
この値をもとに、年間の離婚件数を計算すると、
43,000組 × 5.5% ≒ 約2,365件/年
全国の離婚件数(183,808件)に対しては、およそ1.3%を占めることになります。
④全国平均と比べてどれくらい高い?10倍という現実
カサンドラ層の離婚は年間でおよそ2,365件と推定されました。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
2,365 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.0189/1000人
一方、全国全体の年間離婚率は1.52/1000人です。
つまり、カサンドラ層の離婚率は、全国平均のおよそ1.2%にあたるんですね。
また、年間2,365件という離婚件数は、1日あたりに換算すると…
2,365 ÷ 365 ≒ 約6.5組/日
これは、毎日約6組の「カサンドラ的ストレスを抱えた夫婦」が離婚していることになるんです。
さらに、離婚確率ベースで見るとどうでしょうか?
カサンドラ層の年間離婚確率は 5.5%
全国平均は 0.67%(183,808件 ÷ 2,735万組)なので...
5.5% ÷ 0.67% ≒ 約8.2倍

つまり、カサンドラ的な夫婦は、平均の約8倍の確率で離婚に至っているという計算になります。
SNSと検索データから見えたカサンドラ離婚の現実
①「もう限界」「通じない」…SNSに溢れる本音
SNSでカサンドラ症候群に関する投稿556件を分析したところ、「離婚」や「断絶」といったネガティブな内容が239件、全体の43.0%を占めていました。
特に目立ったのは、「共感されないつらさ」「感情が伝わらない孤独」といったキーワード。
カサンドラ症候群による慢性的なストレスが、リアルな言葉として浮かび上がってきます。
一方で、中立的な内容が158件(28.4%)、ポジティブな内容が159件(28.6%)と、極端にネガティブ一色ではないこともわかりました。
こうした投稿傾向をふまえ、バイアスを軽く補正しつつ実態を反映するかたちで、やや高めに1.1という補正係数を設定しました。
②検索トレンドは地方ほど深刻という傾向
Googleトレンドで「カサンドラ症候群 離婚」というキーワードを分析してみると、2015年頃から徐々に使われ始め、2020年以降は安定して検索されるようになりました。
一時的な流行ではなく、長期的に関心が続いているということだとわかります。
検索が集中している地域を見てみると、秋田・岡山・大分・長野など、いずれも地方エリアが上位に並んでいます。
これは、都市部に比べて支援機関や相談先が少なく、家庭内で孤立しやすい環境が影響しているのかもしれません。
実際に厚労省の「地域保健医療体制調査」でも、地方ほど精神保健福祉士の配置率が低く、相談体制が整っていないというデータがあります。
こうした背景を踏まえると、検索トレンドの偏りには支援格差が表れているとも言えます。
そこで、地域差や検索集中の実情を考慮し、やや高めに1.15という補正係数を設定しました。
③データを掛け合わせて見えたカサンドラ離婚の実態
ここまでで設定したSNS補正係数1.1と、検索トレンド補正係数1.15を掛け合わせます。
1.1 × 1.15 = 1.265
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:2,365件 × 1.265 ≒ 2,993件
年間離婚確率:2,993 ÷ 43,000 ≒ 約6.96%/年
離婚率:2,993 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.0239/1000人
そして、1日あたりに直すと…
2,993 ÷ 365 ≒ 約8.2組/日
つまり、毎日およそ8組の夫婦が、カサンドラ症候群の状態で離婚に至っているということですね。
また、この離婚件数は全国の年間離婚件数183,808件のおよそ1.63%にあたります。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、カサンドラ層は約10.4倍の離婚リスクがあるんです。
今後カサンドラ家庭の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
①支援と理解が進めば…離婚件数が半減する未来とは
まずは、家庭や社会に「カサンドラ症候群の理解と支援」が広がっていく未来から想像してみましょう。
「自治体や医療現場での支援が整っていき、夫婦間でも相互理解を深めることが習慣化する」そんな前向きな未来です。
この場合、現在の年次離婚確率6.96%から、毎年0.3ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
6.96% − (0.3 × 10) = 3.96%
この3.96%の離婚確率を、該当するカサンドラ家庭(43,000組)にあてはめてみると、
年間離婚件数:43,000組 × 3.96% = 約1,703件/年
離婚率:1,703 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.0136/1000人
これは、1日あたりで見れば、約4.7件/日。
ここで注目したいのは、現在の数値(2,993件/年)から約1,290件もの離婚が削減できるということです。

つまり、1日あたり約3.5組の夫婦が離婚を回避できる計算になります。
②支援が届かないと?離婚確率9.96%の悪化シナリオ
一方、相談も受けられないまま、夫婦の対立や家庭内の孤立が深まっていったとしたら…。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.3ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
6.96% + (0.3 × 10) = 9.96%
この9.96%の離婚確率を、同じく該当するカサンドラ家庭(43,000組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:43,000組 × 9.96% = 約4,283件/年
離婚率:4,283 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.0343/1000人
1日あたりでは、約11.7件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の数値(2,993件/年)と比較すると、1年で約1,290件も多くなり、10年で1万2,900件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、9.96%は約14.9倍に相当。

すれ違いが日常になるというだけで、未来にこれだけの差が生まれてしまうのです。
③離婚か共存か、10年後に後悔しないために今できること
ポジティブな未来(3.96%)とネガティブな未来(9.96%)を比べると、たった10年で約6ポイント=約2.5倍もの離婚確率の差がつきます。
離婚率では、0.0136/1000人 vs 0.0343/1000人。
年間離婚件数で見ると、1,703件と4,283件という、なんと2,580件もの違いになります。
この差は、たった一つの支援、たった一つの声かけ、たった一歩の行動が積み重なって生まれるもの。
実際にネット上では、カサンドラ症候群と向き合ってきた経験者から、以下のような声が見られました。
- 専門家に同行してもらい、診察・面談に臨む
ある家庭では、夫が「自分は普通だ」と主張していたため、妻が一人で話すのではなく、第三者である心療内科医に夫婦関係の状況を伝えてもらうことからスタートしました。
妻一人で抱え込むのではなく、専門家の力を借りて対話の場を持つことで、互いの見方に変化が生まれたそうです。 - 信頼できる第三者に記録を見せる
会話がかみ合わない、約束がすぐ忘れられる…そんな日常のズレをその都度「メモに残す」ことで、自分自身の心の整理にもつながります。さらに、その記録をカウンセラーや親、弁護士など信頼できる人に共有することで、孤独感が軽くなったという声もあります。「共感されないつらさ」を、診断の有無にかかわらず言葉にして、外に出すこと。気持ちや困りごとを「書き留めておく」だけでも、後の相談や説明がずっとスムーズになるんです。 - 「自分を守る距離」を具体的に設定する
ある家庭では、週末だけ夫と別居する週末別居を選択。物理的な距離をとることで、精神的な回復の時間を確保できたそうです。距離をとることは逃げではなく、「関係性再構築の準備期間」と考えましょう。 - 支援者や経験者の発信を日常的に取り入れる
「自分だけが苦しんでるんじゃない」と感じられることで、心がフッと軽くなることもあります。
SNSやブログで、同じ経験をしている人たちの言葉に触れることで、自分の気持ちを整理しやすくなるという声も多くありました。自治体の支援講座への参加や、信頼できる書籍で学ぶことも、孤立を防ぐ手段になります。 - 会話はテキストで残す工夫をする
「直接話すと伝わらないけれど、LINEで書くと伝わった」
そんな声もありました。ASDの特性上、文字情報の方が理解しやすい場合もあり、コミュニケーションの形を工夫することで関係が変わっていくこともあるのです。
そして何より大切なのは、「ひとりで抱え込まないこと」。早めに専門家や支援団体に相談してみてください。
実は私自身も、夫にASD傾向があるのでは?と感じて、死を意識するほど追い詰められた時期がありました。
でも、書籍を読んだり、専門家のアドバイスを受けながら、自分の接し方を少しずつ変えていく中で、関係に少しずつ変化が見えてきたんです。
今も手探りではありますが、「夫を責めない姿勢」を持てるようになってからは、夫から敵視されることもなくなり、気持ちがずいぶんと楽になりました。

10年後の自分に「後悔してないよ」と言えるように。今日できる、小さな一歩を踏み出してみませんか。