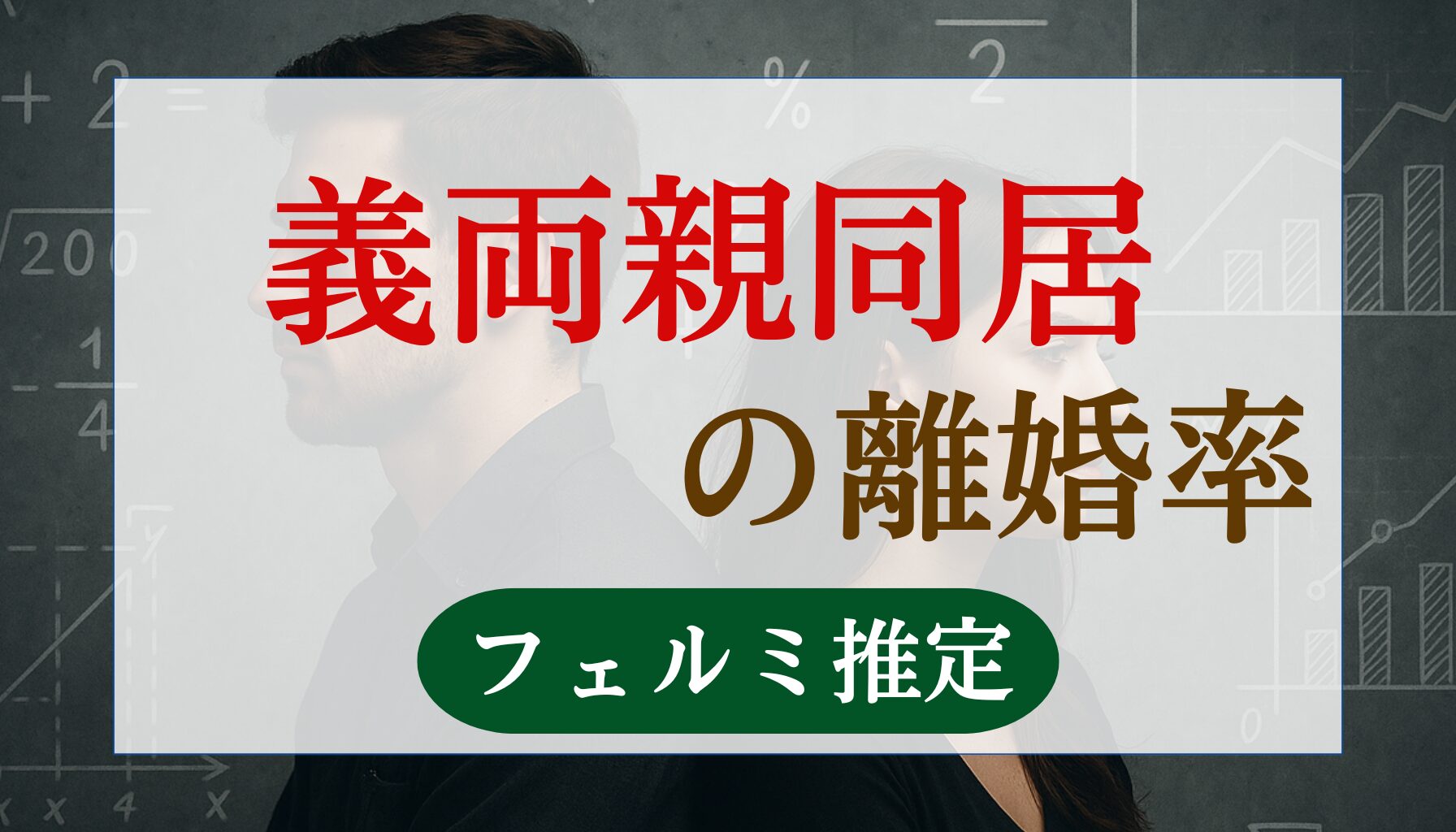義両親と完全同居している夫婦の離婚率、実は0.275/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約14.3%。年離婚確率で見ると、なんと全国平均の約2.06倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
義両親と完全同居する夫婦の離婚率をフェルミ推定してみた【独自分析】
①義両親と完全同居とは?対象夫婦の定義
ここでいう「義両親との完全同居」とは、夫婦がどちらかの親と、同じ家の中で生活している状態です。
敷地内に別棟がある敷地内別居や玄関が別になっている二世帯住宅など、物理的に生活空間が分かれているケースは除外します。
父母と同居している三世代夫婦は年々減っており、1980年は19.9%だったのが、2020年にはわずか7.7%まで減少しているんです(内閣府『男女共同参画白書 2023年』)。
核家族化が進んだ今、義両親との完全同居は珍しい生活スタイルといえます。
②義両親と完全同居している夫婦の割合はどれくらい?
では、義両親と完全に同居している夫婦は、どれくらいいるのでしょうか。
信頼性のある公的データによると、三世代同居の割合は以下の通りです。
- 三世代等の世帯比率:7.7%(内閣府『男女共同参画白書 2023年』)
- 三世代同居世帯数:5.2%(国土交通省『住生活総合調査 2018年』)
- 「児童のいる世帯」に限った三世代世帯:11.2%(厚生労働省『国民生活基礎調査 2023年』)
このように幅がありますが、今回はその中間をとって「完全同居率=7%」と仮定します。
27,350,000 × 0.07 ≒ 約1,915,000組
つまり、全国には約191.5万組の夫婦が、義両親と完全同居していると推定されます。
③調査結果と仮定に基づいた年間離婚確率と件数
では、義両親と完全同居している夫婦のうち、年間でどのくらいのカップルが離婚しているのでしょうか。
Sasaki et al.(2020, Journal of Marriage and Family)によれば、義両親と同居している夫婦は、そうでない夫婦よりも離婚リスクが高まる(調整後オッズ比 1.7倍、妻側親との同居では 2.1倍)という調査結果が出ています。
全国の既婚カップル全体における、年間の離婚確率は0.67%です。
このベース値に「リスク1.7倍」をかけてみると...
1.7 × 0.67% ≒ 1.14%
つまり、義父母と完全同居している夫婦は、1年で約1.14%が離婚していると考えられるわけです。
さらに、完全同居夫婦の数(約191.5万組)に、この確率を掛けて年間の離婚件数を求めてみます。
1,915,000 × 0.0114 ≒ 約21,800件/年
④全国平均と比較して何倍?義両親と完全同居の離婚率
推定によると、義両親と完全同居している夫婦の離婚は、年間でおよそ21,800件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
21,800 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.17/1000人
一方、全国全体の年間離婚率は、1.52/1000人。
つまり、完全同居層の離婚率は、全国平均のおよそ11.2%を占めているんですね。
また、年間21,800件という離婚件数は、1日あたりに換算すると、約60組の夫婦が離婚している計算です。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、義両親と完全同居している夫婦の離婚確率は1.14%。およそ1.7倍のリスクを抱えていることになります。
ただし、ここまでの推計はあくまで統計データをもとにした数字です。
次は、SNSの投稿や検索行動から、より実態に近い数値を出していきましょう。
SNSと検索トレンドから見えた義両親と完全同居する夫婦の実態
①SNS投稿で見えた「限界」「しんどい」の声
SNS上で「義両親との同居」に関する投稿682件を分析してみると、ネガティブ274件・ポジティブ99件・中立309件でした。つまり、ネガティブな内容が40%も占めているという結果に。
具体的な内容としては「風呂を覗かれた」「切迫早産になった」「帰ってこない夫と義両親だけの家にいる不安」など、日常の深刻なエピソードがいくつも確認できました。
投稿を感情面から分類すると、「心理的ストレスや圧迫感」「モラハラやプライバシーの侵害」「価値観のズレ」などが多くを占めています。
一方で、ポジティブな声も15%ほどあり、その多くは「分離型の住居」「義両親の寛容さ」「夫の積極的な協力」がうまくいっている要因になっていました。
全体的には、「義両親との完全同居はリスクが高く、よほどの好条件が揃わないと破綻しやすい」という傾向が強く表れています。
このような傾向をふまえて、SNS補正係数はやや高めに1.15に設定しました。
②Googleトレンドに見る関心の高まりと地域差
Googleトレンドで「義両親 同居」「義母 同居」といったキーワードを調べると、2016〜2020年を中心に、安定した検索が見られました。
とくに検索スコアが多かったのは、山形県(100)、新潟県(75)、福島県(75)、秋田県(62)といった東北〜日本海側のエリアです。
これは、多世代での同居文化や住宅事情など、地域の特性が色濃く反映されていると考えられます。
また、「義母 同居」というキーワードはドラマや報道による検索の山が多く、家庭内の不満が話題になりやすい傾向も確認できました。
一方で、「義両親 同居 離婚」「義両親 同居 ストレス」といったネガティブな検索は散発的にとどまっており、よりリアルな悩みの共有はSNSに流れる傾向があるようです。
こうした検索傾向をふまえ、わずかに高めの1.05という補正係数を設定しました。
③SNSと検索を掛け合わせて見えた義両親と完全同居の離婚率
ここまでで設定したSNS補正係数1.15と、検索トレンド補正係数1.05を掛け合わせます。
1.15 × 1.05 = 1.2075
この補正係数を先ほど算出した数値に掛けていくと...
年間離婚件数:21,800件 × 1.2075 ≒ 26,301件
年間離婚確率:26,301件 ÷ 1,915,000組 ≒ 1.37%/年
離婚率(人口千対):26,301 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.21/1000人
そして、1日あたりに直すと…
26,301 ÷ 365 ≒ 約72組/日
つまり、毎日およそ72組もの「義両親と完全同居」夫婦が離婚している可能性があるということですね。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件のうち、およそ14.3%に相当します。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、「義両親との完全同居」層の離婚確率は1.37%で、約2.06倍のリスクを抱えていることになります。
今後、義両親との完全同居はどうなる?離婚率の未来シナリオ予測
①離婚件数が年1.6万件に減少?話し合い同居準備が進んだポジティブな未来
まずは、日常的に夫婦で話し合い、同居生活に関するルールを作るなどの工夫が当たり前になる未来を想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率1.37%から、毎年0.05ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
1.37% − (0.05 × 10) = 0.87%
この0.87%の離婚確率を、該当する義両親との完全同居世帯(191.5万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:191.5万組 × 0.87% = 約16,661件/年
離婚率:16,661 ÷ 1億2,500万 × 1000 ≒ 0.133/1000人
1日あたりで見れば、約46件/日。
ここで注目したいのは、現在の補正後数値(26,301件/年)から約9,575件もの離婚が削減できるということ。
つまり、1日あたり26組の夫婦が、離婚を回避できる計算になります。

義両親と同居しても続く夫婦関係は、住環境や対話の工夫次第で、十分に実現可能な未来なのかもしれません。
②離婚確率1.87%に上昇?対策せずに同居を続けた場合のネガティブな未来
一方で、夫婦が義両親との同居ルールを話し合わず、生活上の不満を積み重ねていったらどうなるでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.05ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には...
1.37% + (0.05 × 10) = 1.87%
この1.87%の離婚確率を、同じく該当する**完全同居層(191.5万組)**に当てはめてみると、
年間離婚件数:191.5万組 × 1.87% = 約35,811件/年
離婚率:35,811 ÷ 1億2,500万 × 1000 ≒ 0.286/1000人
1日あたりでは、約98件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の補正後数値(26,236件/年)と比較すると、1年で約9,575件も多くなり、10年で9.6万件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、1.87%は約2.79倍に相当。

対策をせずに義両親との同居を始めると、思っていた以上に夫婦関係に負担がかかることもあるんです。
③10年後の差と義両親と完全同居する夫婦が今できること
ポジティブな未来(0.87%)とネガティブな未来(1.87%)を比べると、たった10年で約1.0ポイント=2.15倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率で見ても、0.133/1000人 vs 0.286/1000人。
年間離婚件数では、16,661件 vs 35,811件という、なんと約19,150件もの違いが生まれます。
この差は、完全同居するに当たって夫婦でどれだけ準備をしたかによって変わるんです。
実際にネット上では、次のような対策が取り入れられていました。
- 夫婦で義両親対応ルールを紙に書き出す
ある家庭では、「家事の分担は?」といった曖昧なルールを夫婦で紙にまとめました。 書面にすることで、感情的にならず冷静に話し合えるようになり、意見の食い違いも減ったといいます。 義両親にも「これが私たちのルールです」と説明できるため、トラブル回避に役立っています。 - 夫が味方だと分かる言動を意識する
義両親との間に立つ夫がどっちつかずだと、妻側の不満が爆発しやすい傾向があります。 ある妻は「夫が“ごめん、俺がうまく言うから”って言ってくれただけで、救われた」と振り返ります。 物理的な対応よりも、「自分の味方だ」と分かる一言の方が、精神的にはるかに効くようです。 - 同居前に絶対NG条件を夫婦で確認する
ある夫婦では、「週1以上の干渉は禁止」「居室へのノックなし訪問は即注意」といった絶対NG条件をあらかじめ定めました。 明確な地雷回避が、円満な同居の鍵になったとのことです。 - 子育て感覚の違いをあえて言葉にして共有する
「昔は放って育てた」「今は過干渉すぎる」と世代間で子育て方針がズレるのは当然です。 ある家庭では、妻が「夜9時以降は静かに過ごしたい」「甘いお菓子は控えたい」など、具体的な方針を義両親に伝えました。 最初は驚かれましたが、「ちゃんと理由がある」とわかると、少しずつ距離感を調整してくれたそうです。 - 家事の正解を義母とすり合わせる時間をとる
「なぜ干し方が違うの?」「なんでそんな順番なの?」と、家事観の違いは意外な火種になります。 ある家庭では、休日にあえて義母と一緒に家事を行い、「私のやり方はこうです」と伝えたそうです。 面と向かって伝えるのは勇気がいりますが、実際には「なるほどね」と納得されたとのこと。 違いを否定ではなく共有に変える工夫が、関係改善につながったようです。 - 生活導線を「分離」するプチリフォームを検討する
ある家庭では、義母と毎朝顔を合わせることがストレスでしたが、キッチンと洗面所の使用時間をずらし、簡易カーテンで仕切ることで緊張感が大きく軽減されたそうです。「一緒に住む」と「すべてを共有する」は別。ちょっとした距離感が心を守ってくれるんですね。 - トイレ・風呂だけは「別」にする徹底策をとる
義父との共有がストレスになっていたある家庭では、トイレと浴室だけを外付けリフォームし、「同じ家だけど別生活」の感覚を実現。「あの改装がなければ離婚してたかも」と話しています。
義両親との完全同居は、気を遣いすぎたり、つい我慢を重ねてしまうもの。
でも、「事前にルールを作る」「自分の価値観を伝える」など、いくつかの小さな取り組みが大きな効果を生むこともあります。

10年後のあなたが、「同居してよかった」と言えるかどうかは、今日のひと工夫から始まりますよ。