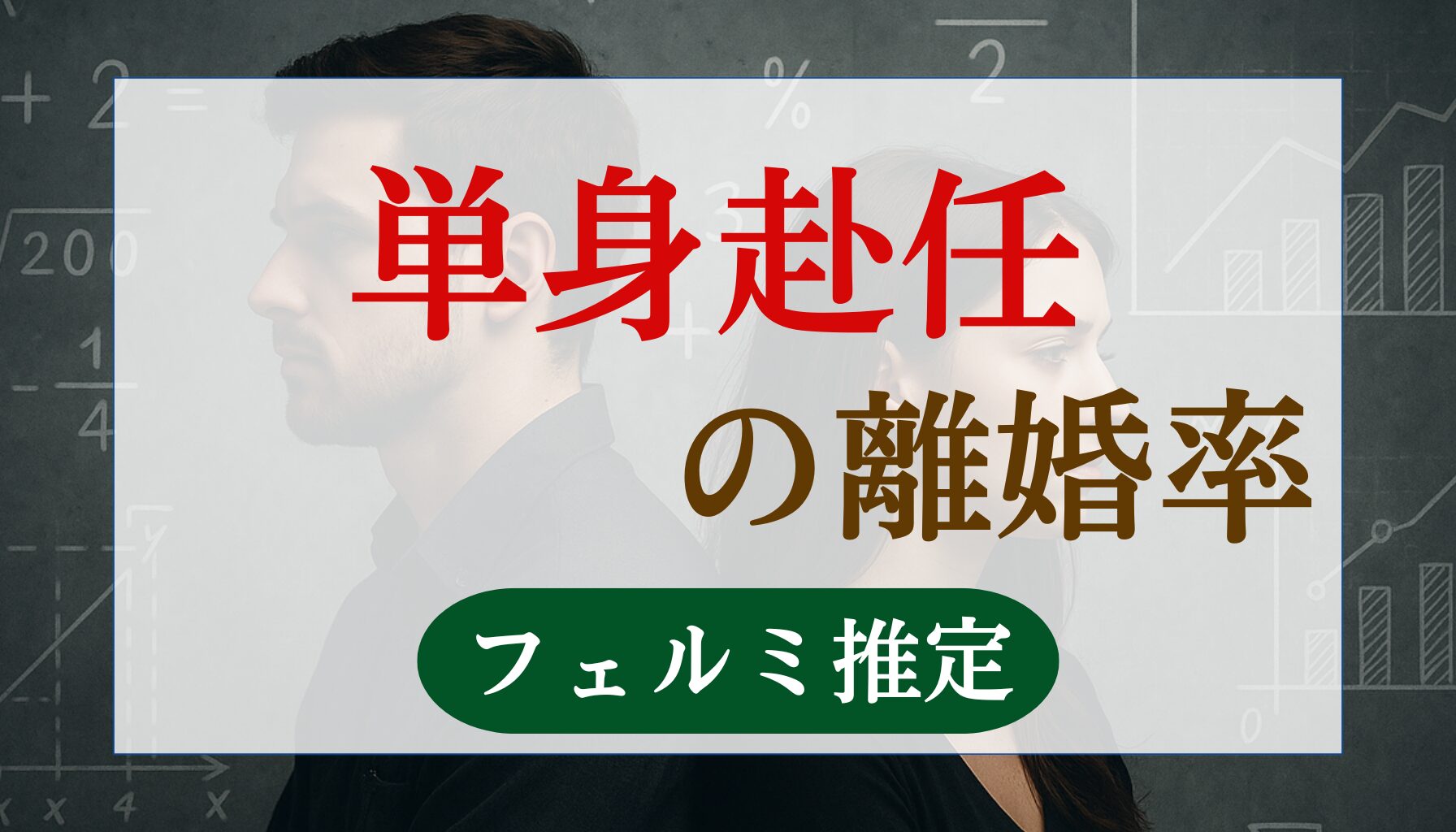単身赴任の離婚率、実は0.027/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約1.84%。しかし、年離婚確率で見ると、なんと全国平均の約2.8倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
単身赴任の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①単身赴任とは?対象となる夫婦の定義
ここで扱う「単身赴任夫婦」は、日本国内で別居しながら生活している既婚者(主に男性)とその配偶者を指します。
企業の人事異動や業務命令などで物理的に距離ができ、面会は週末や月数回と限られるのが一般的です。
そのため、日常の家事や育児は、家に残った側が担うことが多く、その分ストレスや負担が偏りがちに。
こうした生活環境が、夫婦のコミュニケーションや関係性に影響し、離婚リスクを高めると考えられています。
②単身赴任中の夫婦はどれくらい?全国に何組いるのか
まず、単身赴任中の夫婦がどのくらいいるかを推定します。
既婚カップル数は約27,350,000組(厚労省『国民生活基礎調査(2023年)』より)。
そのうち、別居している夫婦は全体の1.1%です。
別居夫婦のうち60%が単身赴任によるものと仮定すると...
27,350,000 × 0.011 × 0.60 = 180,810組
よって、全国には約18.1万組の単身赴任夫婦がいると見込まれます。
③仮定と調査に基づく年間離婚確率と件数は?
次に、単身赴任家庭の年間離婚確率を見ていきます。
5年間での累積離婚確率は以下の通りです:
単身赴任夫婦:7.3%
非単身赴任夫婦:4.1%
(出典:Social Science Japan Journal『Marital Stability and Long-Distance Commuting in Japan』)
これを年率に換算すると:
年率 = 1 − (1 − 0.073)^(1/5) ≒ 1 − 0.9852 ≒ 約1.48%/年
つまり、単身赴任夫婦が1年以内に離婚する確率は約1.48%です。
さらに、これを件数に換算すると:
180,810組 × 0.0148 = 約2,675件/年
④単身赴任の離婚率は全国平均の何倍?
推定によると、単身赴任世帯の離婚は年間でおよそ2,675件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
2,675 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.021/1000人
一方、全国全体の年間離婚率は1.52/1000人です。
つまり、単身赴任層の離婚率は、全国平均のおよそ1.38%を占めているんですね。
また、年間2,675件という離婚件数は、1日あたりに換算すると...
2,675 ÷ 365 ≒ 約7.3組/日
毎日約7組の夫婦が、単身赴任をきっかけに別れを選んでいるという計算です。

既婚層全体の離婚確率(0.672%)と比べると、単身赴任世帯は1.48%で約2.2倍の離婚リスクがあるという結果になりました。
SNSと検索データから見えた単身赴任離婚の現実
①SNS投稿から読み取れる「孤独」「共感できない」の声
SNS投稿483件をもとに、単身赴任にまつわる本音を分析しました。
ネガティブな投稿が全体の41.8%と最も多く、「孤独感」「精神的なつらさ」「共感されないもどかしさ」といった言葉が目立ちます。
「育児の限界で涙が止まらなかった」「心療内科に通うほどしんどい」など、精神的負荷の大きさが投稿から伝わってきました。
その背景には「役割分担の偏り」や「制度への不満」など、生活と仕組みのギャップがあるようです。
ポジティブな声も31.5%ほどあり、「再会の嬉しさ」や「自分時間が持てた」といった前向きな体験も見られましたが、全体ではネガティブ感情が優勢という結果でした。
このような感情バランスの偏りを考慮し、SNS上の声に対する補正係数は、やや高めに1.15を設定しました。
②Googleトレンドで見る地方ほど強い不安感
「単身赴任 離婚」というキーワードの検索ボリュームは、2010年前後から上昇し、特に2015年前後まで高い関心が続いていました。
近年やや落ち着きつつあるものの、依然として検索ニーズは残っており、単身赴任と離婚の関連性が多くの人の関心事であることが分かります。
地域別に見ると、検索ボリュームが特に高かったのは宮崎県・北海道、そのほか山口県・静岡県・香川県なども上位に入りました。
これらの地域は、共働き率が低めで、保育所整備や時短勤務制度の導入も都市部ほど進んでいない傾向があります。
つまり、仕事と家庭の両立が難しい地域ほど、単身赴任中の心理的ストレスや不安が強まりやすいという現実があるわけです。
こうした地域格差や継続的な関心をふまえつつも、「検索は必ずしも悩みの表れとは限らない」という特性を考慮し、Google検索の感情補正としては、控えめに1.1という補正係数を設定しました。
③SNS×検索で見えた「家族と心がすれ違う瞬間」
ここまでで設定したSNS補正係数1.15と、検索トレンド補正係数1.1を掛け合わせます。
1.15 × 1.1 = 1.265
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:2,675件 × 1.265 ≒ 3,384件
年間離婚確率:3,384 ÷ 180,810 ≒ 1.87%/年
離婚率:3,384 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.027/1000人
そして、1日あたりに直すと…
3,384 ÷ 365 ≒ 約9.3組/日
つまり、毎日およそ9組の夫婦が、単身赴任によって離婚に至っているということですね。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件のおよそ1.84%にあたります。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、単身赴任層は約2.8倍の離婚リスクがあるんです。
今後単身赴任世帯の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
① 離婚率が半減?夫婦の工夫と支援がつくる「安定した未来」
まずは、「テレワークや帰省手当など企業の配慮が進み、夫婦もアプリや通話で関係維持の努力を続けている」という前向きな未来から想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率1.87%から、毎年0.15ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
1.87% − (0.15 × 10) = 0.37%
この0.37%の離婚確率を、該当する単身赴任世帯(約18.1万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:181,000組 × 0.0037 ≒ 約669件/年
離婚率:669 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 約0.012/1000人
1日あたりで見れば、約1.8件/日。
ここで注目したいのは、現在の数値(3,384件/年)から約2,700件もの離婚が削減できるということです。
つまり、1日あたり約7組の夫婦が離婚を回避できる計算になります。

単身赴任でも、夫婦が向き合う工夫を続ければ、離れていても安心できる家庭はつくれるんです。
② 離婚率3.37%に上昇?放置とすれ違いが続く「崩れゆく未来」
一方、「転勤制度が改善されなかったり、夫婦間の感情の共有が途絶えた状況」が続いたとしたらどうなるでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.15ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
1.87% + (0.15 × 10) = 3.37%
この3.37%の離婚確率を、同じく該当する単身赴任世帯(約18.1万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:181,000組 × 0.0337 ≒ 約6,094件/年
離婚率:6,094 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 約0.042/1000人
1日あたりでは、約16.7件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の数値(3,384件/年)と比較すると、1年で約2,700件も多くなり、10年で2万7,000件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、3.37%は約5倍に相当。

何も工夫しなければ、「気づいたら他人」になってしまう...そんな10年後が待っているかもしれません。
③ 10年後の“差”と、今できる対処策
ポジティブな未来(0.37%)とネガティブな未来(3.37%)を比べると、たった10年で3.0ポイント=約9倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.012/1000人 vs 0.042/1000人。
年間離婚件数では669件と6,094件という、なんと5,425件もの違いが生まれます。
この差は、ふたりの距離ではなく、「向き合う習慣」があるかの違いかもしれません。
実際にネット上では、単身赴任のすれ違いに悩みながらも、工夫で乗り越えてきた声も見られます。
- 会話の内容を「子ども以外」にも広げる
ある家庭では、毎回の電話が子どもの報告ばかりで、会話が単調になっていたそうです。 意識して「最近の趣味」や「昔話」を挟むことで、夫婦らしいやりとりが復活したという声がありました。 - 気づいたときだけ連絡OKにする
毎日の報連相が妻にとって負担になっていたというケースでは、「義務」ではなく「気づいたときに連絡するスタイル」に変えたことで、関係が改善したといいます。 距離のある生活では、無理な習慣よりも心地よさが継続の鍵になります。 - たとえ手伝っても、感謝の言葉を忘れない
「帰省して子どもの送り迎えをしても当然とされてモヤモヤした」という投稿も見られました。 些細な手伝いでも「ありがとう」と言い合うだけで、役割意識が対等になり、協力し合いやすくなったという声があります。 - 子どもの変化を動画やメモで共有する
写真だけでは伝わりにくい日々の成長を、短い動画や一言メモで夫に送っていた家庭があります。 「その場にいたような実感がわく」と、父親の孤立感が減り、会話が自然に増えていったそうです。 - 定期的に「考えのズレ」を確認する
単身赴任中に「価値観が離れていった」という声が多くあります。 ある家庭では、月に一度「最近変わった考え」や「相手に聞きたいこと」をテーマに、ビデオ通話で話す習慣をつくったことで、ズレをその都度埋められるようになったとのことでした。
単身赴任が変えるのは、物理的な距離ではなく、日々の気持ちの繋がりかもしれません。
声をかける一手間、感謝を伝えるひとことが、すれ違いは防げるものです。

10年後、離れていた時間がつながりを深めた時間だったと思えるかは、いまの一歩で決まります。