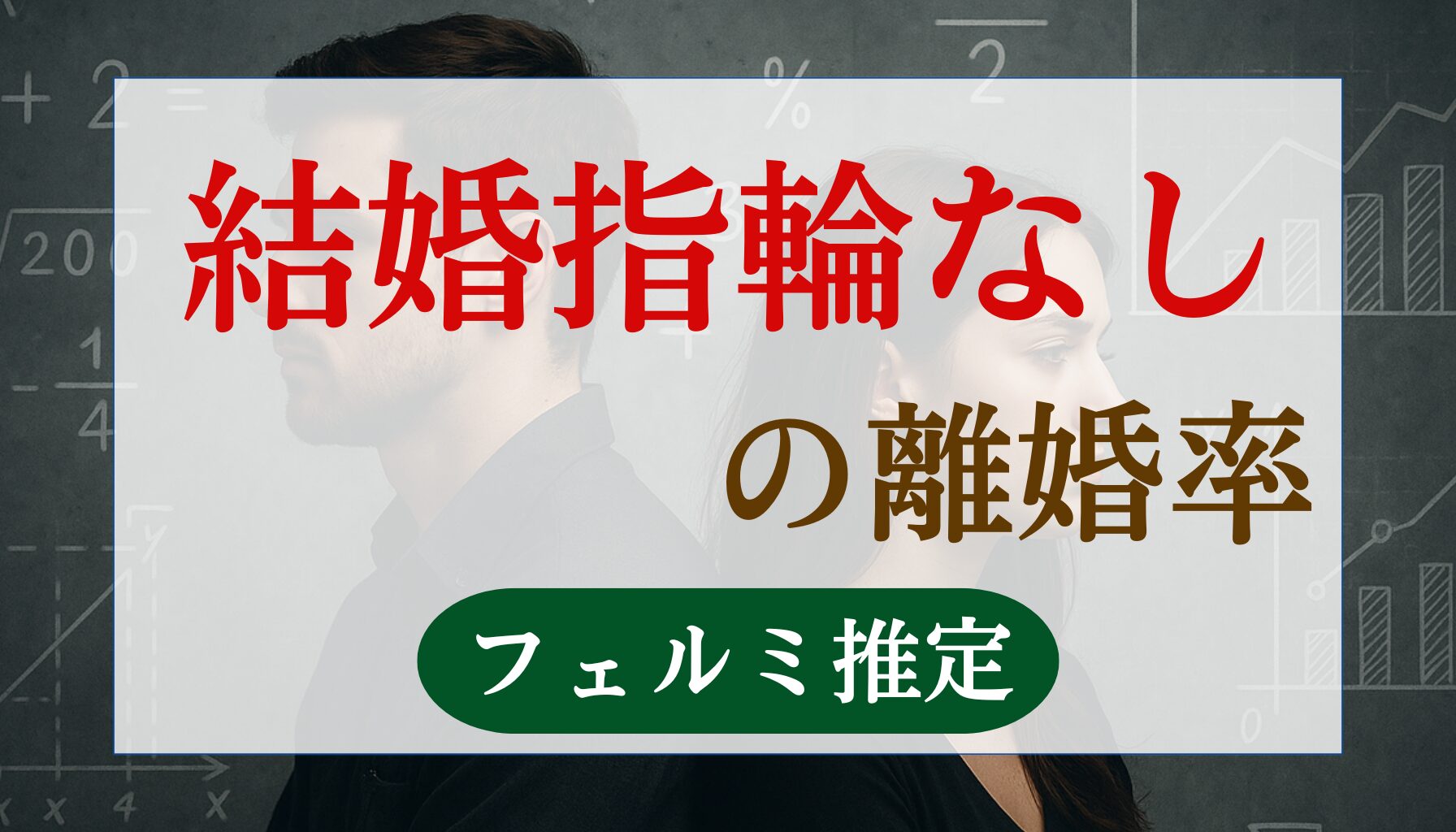結婚指輪なし夫婦の離婚率、実は0.36/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約24.5%。年離婚確率で見ると、なんと全国平均の約1.32倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
結婚指輪なし夫婦の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①結婚指輪なし夫婦とは?定義と前提条件
ここで言う「結婚指輪なし夫婦」とは、法律的には結婚しているけれど、結婚指輪を購入・交換・保有していないカップルのことです。
記念用のペアリングや写真など他の方法で絆を表しているケースや、婚約指輪だけを贈った場合などは含みません。
結婚指輪の有無が離婚とどう関係しているかを示す公的データは、今のところ存在していません。
そのため今回は、挙式を行ったかどうかや婚約指輪の購入状況などの関連データをもとに、「結婚指輪なし夫婦」の層を推定していきます。
②日本における結婚指輪なし夫婦の割合を推定
現在、日本にいる既婚カップルの数は約2,735万組です(厚生労働省『国民生活基礎調査(2023年)』)。
このうち、「結婚指輪をしていない夫婦」がどれくらいいるのかを、いくつかのデータと仮定を使って計算していきます。
- 結婚式を挙げない「ナシ婚」の割合:54.7%(マイナビ『2023年 結婚・結婚式の実態調査』)
- 婚約指輪を購入しなかった割合:34.3%(WeddingPark『婚約指輪に関するアンケート(2021年)』)
これを踏まえて以下のような仮定を立てました。
- ナシ婚の人のうち、指輪も省略する割合=30%
- 結婚式を挙げた人でも、指輪を買わない割合=5%
そうすると結婚指輪なしの割合は...
=(ナシ婚割合)×30% +(挙式あり割合)×5%
= 0.547×0.30 + 0.453×0.05 ≈ 0.1868(≒18.7%)
つまり、「結婚指輪なし夫婦」は全体の約18.7%と推定されます。
これを人数に換算すると...
2,735万組 × 18.7% ≈ 510.8万組
③年間離婚確率と件数を仮定から算出
では、510.8万組の結婚指輪なし夫婦が1年のうちにどのくらい離婚しているのか、確率と件数で見ていきましょう。
まず、日本の年間の離婚件数は 183,808組で、年間離婚確率は0.67%/年です(厚生労働省『人口動態統計月報年計(2023年)』)。
一方、婚約指輪なしの人は、そうでない人より1.27倍離婚しやすいと推定されています(参考:婚約指輪なしの離婚率)。
結婚指輪なし層もこれに近い傾向と仮定すると...
0.67% × 1.27 ≈ 0.85%/年
これを510.8万組にあてはめると、
510.8万組 × 0.85% ≈ 43,461件/年
④全国平均の離婚率と比較して高いのか?
推定によると、「結婚指輪なし夫婦」の離婚は、年間でおよそ43,461件にのぼります。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
43,461 ÷ 125,000,000 × 1000 ≈ 0.35/1000人
一方で、全国全体の年間離婚率は1.52/1000人です。
つまり、「結婚指輪なし夫婦」の離婚率は、全国平均のおよそ23%(0.35/1.52)を占めているんですね。
また、年間43,461件という離婚件数は、1日あたりに換算すると約119組。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、結婚指輪なし層の離婚確率は0.85%で、離婚リスクは約1.27倍なんです。
ただし、ここまでの推計はあくまで統計データをもとにした数字です。
次は、SNSの投稿や検索行動から、より実態に近い数値を出していきましょう。
SNSと検索データから見えた結婚指輪なし夫婦の離婚リスク
①SNS投稿から見えた「不満」「覚悟がない」の声
SNS上で「結婚指輪なし」に関する投稿を分析すると、ネガティブ:121件、ポジティブ:98件、中立:151件と、ややネガティブな意見が目立つ結果でした。
その中身を見てみると、「プロポーズも指輪もなかった」「ちゃんと愛されてるのか不安になる」「虚無感でいっぱいになる」といったような、不安や寂しさを綴る声が多く見られます。
中には、「喧嘩になると『ここは俺の家』と線引きされる」「インスタで他の人の指輪を見て、心が沈む」といった投稿も。
こうした声からは、指輪が単なる装飾品ではなく、夫婦間の愛情・覚悟・対等さを感じるうえで大きな意味を持つことが読み取れます。
このような傾向をふまえて、「結婚指輪なし夫婦」はやや離婚リスクが高まると見て、やや高めに1.01という補正係数を設定しました。
②Googleトレンドで見えた「結婚指輪なし」への関心の広がり
Googleの検索データで「結婚指輪なし」というキーワードを分析すると、2015年から増加傾向が強まり、2018年以降は高水準で推移しています。
また、地域別では、香川・愛媛・岩手・山形・福岡などで検索が多く、都市部では「選ばれる価値観」、地方では「珍しい選択肢」として注目されているような傾向も見られます。
こうしたトレンドをふまえ、検索側の補正係数も、やや高めに1.03と設定しました。
③感情とデータが交差する、離婚リスクの実態とは?
ここまでで設定したSNS補正係数1.01と、検索トレンド補正係数1.03を掛け合わせます。
1.01 × 1.03 = 1.0403
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:43,461件 × 1.0403 ≒ 45,161件
年間離婚確率:45,161 ÷ 510.8万組 ≒ 0.884%/年
離婚率:45,161 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.36/1000人
これは1日あたりで考えると、毎日およそ124組もの「結婚指輪なし」夫婦が離婚しているということなんです。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件のおよそ24.6%にあたります。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、「結婚指輪なし夫婦」は約1.32倍の離婚リスクがあるんです。
今後「結婚指輪なし夫婦」の離婚率はどうなる?10年後の未来シナリオ
①離婚件数が半減?社会の理解や夫婦間の納得が進んだ未来
まずは、結婚指輪がない夫婦でも「ちゃんと絆がある」という理解が広がり、夫婦もお互いに納得して結婚指輪を持たない選択をするようになった未来を想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率0.884%から、毎年0.05ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.884% − (0.05 × 10) = 0.384%
この0.384%の離婚確率を、該当する結婚指輪なし夫婦数(510.8万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:510.8万組 × 0.384% = 約19,626件/年
離婚率:19,626 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.157/1000人
1日あたりで見れば、約54件/日。
ここで注目したいのは、現在の数値(45,161件/年)から約25,500件もの離婚が削減できるということです。
つまり、1日あたり約70組の夫婦が離婚を回避できる計算になります。

多様な結婚のかたちを尊重し、指輪の有無にとらわれない社会が広がれば、それだけで多くの夫婦が関係を維持しやすくなるんですね。
②離婚確率1.3%超?価値観のズレが拡大した未来
一方で、「結婚指輪がないなんて信じられない」といった価値観が主流になり、結婚指輪を持たない夫婦が周囲の理解を得られないような状況が続いたとしたらどうなるでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.05ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.884% + (0.05 × 10) = 1.384%
この1.384%の離婚確率を、同じく該当する結婚指輪なし夫婦数(510.8万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:510.8万組 × 1.384% = 約70,706件/年
離婚率:70,706 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.566/1000人
1日あたりでは、約194件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の数値(45,161件/年)と比較すると、1年で約25,545件も多くなり、10年で25万件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、1.384%は約2.07倍に相当。

周囲の視線や思い込みにさらされ、気持ちを言葉にできなくなる状況が続くと、それだけで夫婦関係は急激に冷えてしまうこともあり得るのです。
③「結婚指輪なし」の未来を左右する分岐点と、今できること
ポジティブな未来(0.384%)とネガティブな未来(1.384%)を比べると、たった10年で約1.0ポイント=3.6倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.157/1000人 vs 0.566/1000人。
年間離婚件数では19,626件と70,706件という、なんと51,080件もの違いが生まれます。
この差は、「結婚指輪がない」ことそのものではなく、それをどう認識し合い、受け止められるかの違いによって生じるんです。
実際にネット上では、「形がなくても、2人だけの記念をつくっている」という工夫も多く見られました。
- 形式がないからこそ、思い出づくりを意識する
ある女性は、結婚指輪も結婚式も写真もなしで入籍したものの、それが心残りで離婚への後押しになったと振り返っています。再婚後は、形はなくても、入籍記念の写真、手紙、イベントなど、自分たちなりの思い出を共有することで絆を感じることがきたとのこと。 - お金の使い方を2人で決める
指輪や式にお金をかけるかどうかで価値観がぶつかる夫婦は少なくありません。ある投稿者は「妻が効率重視で、指輪代をハネムーンに回した」とのこと。選択肢に正解はなくても、「2人で納得して決めること」が重要だという意見です。 - 指輪をしない代わりに気持ちを伝える習慣を持つ
「結婚指輪をしない=気持ちがない」と受け取られてしまうこともある中で、ある家庭ではお互いの気持ちを定期的に確認し合っているそうです。大事なのは「形がなくても大切にしている」ということを示すことなんですね。 - 外部からの視線に惑わされない視点を持つ
「結婚式も指輪もないけど幸せ」という夫婦もいます。大切なのは、他人の目を気にすることではなく、2人が納得して安心できる関係を築けているかです。人と比べない視点が、自分たちの絆を守る鍵になりますよ。
「結婚指輪がない夫婦は離婚しやすい」と一括りにするのは簡単です。
でも、本当に大事なのは、結婚の証よりも心の共有をできているかどうか。

形のない関係だからこそ、日々の言葉や工夫で強い絆を育むことができますよ。