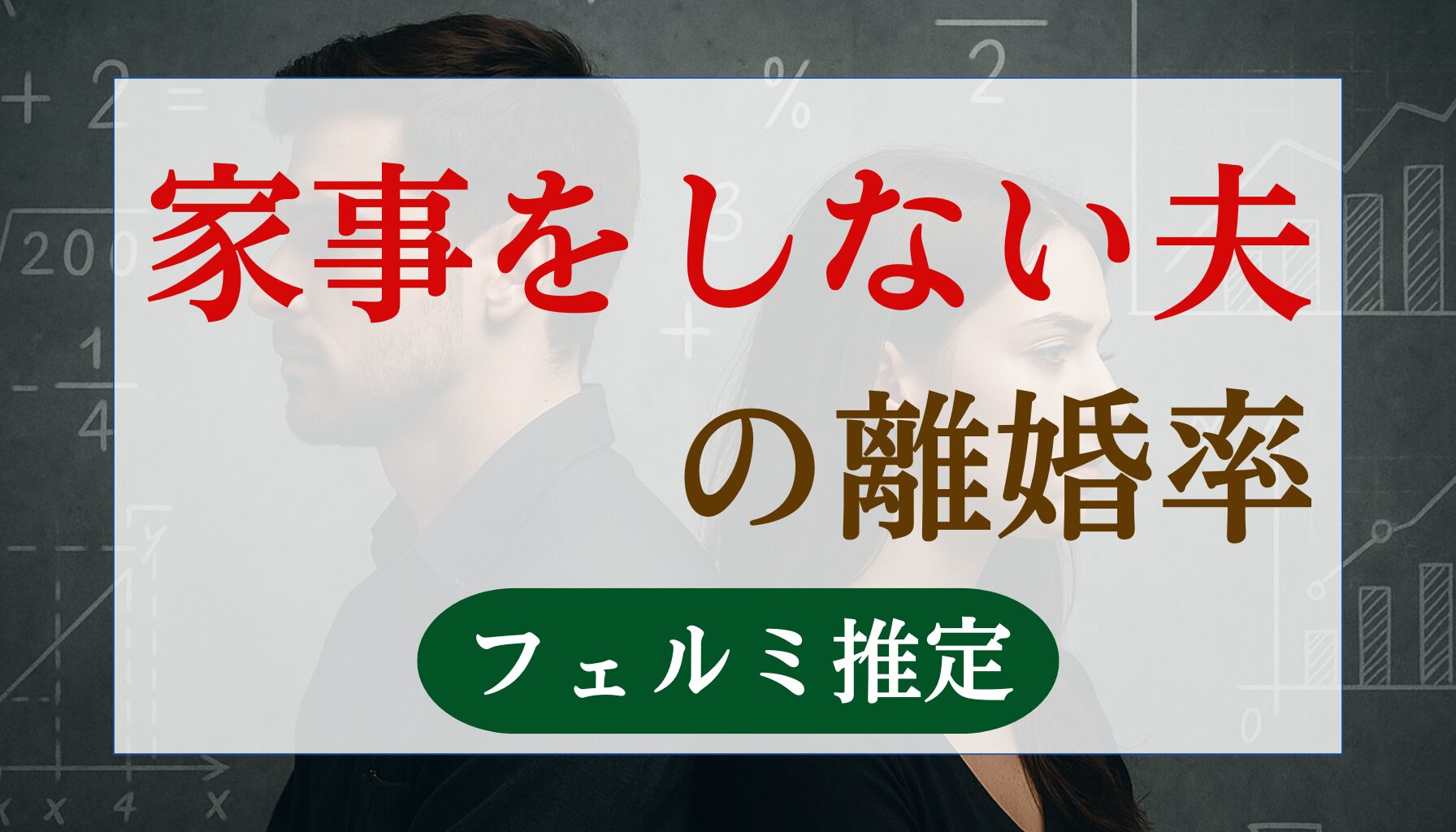家事をしない夫の離婚率、実は0.49/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約33.6%。年離婚確率で見ると、なんと全国平均の2.1倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
家事をしない夫の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①「家事をしない夫」とは?対象となる家庭の定義
まずは「家事をしない夫」について定義します。
ここで対象になるのは、
- 家事時間が1日1時間未満の夫
- 妻が夫の家事参加に不満を持っている
という、2つの条件を満たす家庭としました。
つまり、客観的に家事をしていないだけでなく、主観的にも不満を持たれているというダブル条件からの定義です。
こうした家庭は、家事分担をめぐってすれ違いが起きやすく、離婚リスクが高まりやすいと考えられます。
②家事をしない夫の割合は?不満を抱える妻の実態
どのくらいの家庭がこの条件にあてはまるのかを、2つの統計から推定します。
- 「家事時間が1日1時間未満の夫」は約40%(内閣府『男女共同参画白書(2022年)』)。
- 「夫の家事参加に不満を持っている妻」も約40%(国立社会保障・人口問題研究所『全国家庭動向調査(2022年)』)。
この2つを掛け合わせて、両方の条件を満たす家庭の割合を推定すると…
0.40 × 0.40 = 0.16(16%)
この割合を既婚世帯全体にかけると、
2,735万組 × 0.16 = 約437.6万組
つまり、日本には「家事をしない夫がいる家庭」が、約437万組あると推定できます。
③ 推定離婚確率は1.07%?年間46,819件にのぼる衝撃数値
次に、「家事をしない夫」世帯における離婚確率と件数を見ていきます。
全国の年間離婚件数は183,808件(厚労省『人口動態統計(2022年)』)で、全体の既婚カップルに対する年次離婚確率は…
183,808 ÷ 27,350,000 ≒ 0.67%
一方、東京大学(2019年)とパーソル総研(2023年)の分析では、「家事をしない夫」を持つ家庭の離婚リスクは通常の1.5〜1.8倍。
中間値の1.6倍を採用すると、該当層の離婚確率は…
0.67% × 1.6 = 1.07%/年
これを該当する437.6万組に当てはめると…
437.6万組 × 1.07% = 約46,819件/年
④ 離婚率は全国平均の2倍!家庭に潜む高リスク
推定によると、「家事をしない夫」世帯の離婚は年間でおよそ46,819件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
46,819 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.37/1000人
一方、全国全体の年間離婚率は1.52/1000人です。
つまり、「家事をしない夫」世帯の離婚率は、全国平均のおよそ2.1倍(約37%)にあたるんですね。
また、年間46,819件という離婚件数は、1日あたりに換算すると…
46,819 ÷ 365 ≒ 約128組/日

これは、毎日およそ128組の「家事をしない夫婦」が離婚していることになるんです。
SNSと検索データから見えた「家事しない夫」と離婚の現実
①「もう限界…」妻たちの本音と離婚へのカウントダウン
SNS上の投稿を調査すると、「家事をしない夫」への感情は、ほとんどがネガティブであることが分かりました。
分析対象の投稿件数は、ネガティブが96件、ポジティブ(改善型の夫に対する評価)が27件、中立が20件。
なんと、「家事をしない夫」そのものを明確に肯定する投稿は、ゼロでした。
「共働きなのに夫が家事しない」「手伝ってやってるという態度が腹立つ」「義家族の家父長的な古い価値観」など、単なる愚痴というより、「家事は女がやるもの」という古い風潮への怒りが多く見られました。
投稿の内訳を見ると、「共働きなのに夫が家事しない」が30件、「夫の手伝い意識や過剰な自己評価への反発」が18件、「モラハラ・家庭内の力関係」が13件などに分かれ、家庭内のバランスや価値観のズレが背景にあるようです。
こうした傾向から見えてくるのは、「家事しない夫=家庭内不平等の象徴」として捉えられている現実。
これは個人の努力だけで解決する問題ではなく、社会全体の問題でもあるといえるでしょう。
分析の結果、ネガティブ投稿の比率はおよそ65%(96 ÷ (96+27+20) ≒ 65%)。
このような感情の強さを考慮し、SNS補正係数は最大の1.2に設定しました。
②検索トレンドから見る“見えない不満”の蓄積
Googleトレンドの検索データでも、「夫 家事 しない」というキーワードは2010年頃から増加傾向を見せています。
特に2021年以降には急激な上昇もあり、社会全体での関心やストレスの高まりがうかがえます。
「家事をしない夫 離婚」といった検索も散見され、今すぐ離婚とはいかなくても、じわじわと不満が蓄積している様子が分かります。
また、地域別のデータでは、山梨県・熊本県など家父長的な文化が残る地域で検索数が高く、地域性との関連もありそうです。
こうしたトレンドをもとに、検索に基づく補正係数は1.1と設定しました。
③共感と怒りが交錯…ネット上に現れたリアルな離婚兆候
ここまでで設定したSNS補正係数1.2と、検索トレンド補正係数1.1を掛け合わせます。
1.2 × 1.1 = 1.32
この補正係数をもとに、最初に推定された離婚件数に反映していきます。
年間離婚件数:46,819件 × 1.32 ≒ 61,801件
年間離婚確率:61,801 ÷ 4,376,000 ≒ 1.41%/年
人口ベース換算の離婚率:61,801 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.49/1000人
さらに1日あたりで換算すると…
61,801 ÷ 365 ≒ 約170組/日
つまり、毎日およそ170組の夫婦が、家事をしない夫がいることを背景に離婚しているということになります。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件のうち、約33.6%を占める割合です。
既婚層全体の平均離婚確率(0.67%)と比較すると、「家事しない夫」層は約2.1倍の離婚リスクを抱えていることになります。

こうして見てみると、「夫が家事をしない」ということは、単なる家庭内の不満ではなく、離婚の深刻な原因のひとつであることがよくわかります。
今後「家事をしない夫」家庭の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
① 離婚件数が半減?意識改革と支援で広がるポジティブ未来
まずは、「夫の家事参加が進み、支援制度も充実した未来」を想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率1.41%から、毎年0.1ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
1.41% − (0.1 × 10) = 0.41%
この0.41%の離婚確率を、該当する「家事をしない夫」世帯数(437.6万組)に当てはめてみると、
離婚件数:437.6万組 × 0.41% = 約17,942件/年
離婚率:17,942 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.14/1000人
ここで注目したいのは、現在の補正後数値(61,801件/年)から、約43,859件もの離婚が削減できるということ。
つまり、1日あたり約120組の夫婦が、離婚を回避できる可能性があるんです。

「夫も家事をするのがあたりまえ」そんな家庭が増えると、離婚しにくい未来がちゃんと見えてくるんです。
② 離婚確率が2.4%へ?夫の変化なしで進むネガティブ未来
一方で、支援や制度が広がらず、夫の行動も変わらないまま10年が過ぎたとしたらどうでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.1ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
1.41% + (0.1 × 10) = 2.41%
この2.41%の離婚確率を、同じく437.6万組の世帯にあてはめてみると、
離婚件数:437.6万組 × 2.41% = 約105,457件/年
離婚率は、105,457 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.84/1000人
1日あたりに換算すると、105,457 ÷ 365 ≒ 約289件/日。
これは現在よりおよそ1.7倍の件数増加であり、全国の離婚件数183,808件のうち57.4%を占める計算になります。

既婚層の平均離婚確率(0.67%)と比べても、約3.6倍のリスクという深刻な数値です。
③ 10年後に後悔しないために…今すぐ始めたい「夫を動かす」行動リスト
ポジティブな未来(0.41%)とネガティブな未来(2.41%)を比べると、たった10年で約2.0ポイント=約6倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.14/1000人 vs 0.84/1000人。
年間離婚件数では17,942件と105,457件という、なんと約8万7,500件もの違いが生まれるんです。
この差は、「家事」という日々の行動が、家族の未来にいかに影響するかを物語っています。
実際にネット上では、家事分担に悩む家庭がさまざまな工夫をして、状況を変えてきた声も見られます。
- 家事の流れを見える化して共有する
分担表や家事ルーティンを紙に書き出し、冷蔵庫や玄関に貼り出す工夫。 「夫がこんなにやってたの?と驚いた」という声も。 視覚的に共有することで、家事の存在と偏りに夫自身が気づくきっかけになります。 - ありがとうを先に伝える
「感謝されたことで続けようと思えた」という反応も多く見られます。 指摘より先に承認することで、協力的な空気が生まれやすくなります。 - 家事を選ばせて任せる
「どれをやるか夫に選ばせる」と、やらされ感が減って継続しやすいという声。 自主性が尊重されることで、責任感と満足度が同時に得られる仕組みです。 - ダイエットだからと理由をすり替える
「ダイエットだから階段掃除して」「風呂掃除は筋トレになるよ」など、 家事に前向きな理由をつけてお願いする手法。目的をずらすことで抵抗感を減らすアイデアです。 - 病気かもと悲壮感で揺さぶる
言ったことをできない夫に「脳の病気かも?病院でMRI撮ってもらおうよ」と本気で心配したフリをして行動に変化が見られたというケースも。 悲壮感を演出することで、現実を直視させた家庭もありました。 - 家事をゲーム化・ポイント制にする
アプリやポイント表を導入して、達成感や報酬を設定。 「やらされ感」が減り、自発的に続けやすくなる工夫です。 - やってほしいことを具体的に伝える
「もっと手伝って」ではなく「今夜はお皿洗いお願い」のように明確に伝えるだけで、 夫の行動が変わったという声も多く、意外と効果的な基本策です。 - 離婚カードを現実として示す
実際に離婚届を見せたり、両家を交えて家族会議を開くなど、 危機感を伝えて初めて夫が本気になったという家庭も存在します。 - 「自分でやらないならお金で解決」作戦
どうしても動かないときは、夫のお金から時短家電の購入や家事代行サービスの利用を提案した家庭も。
夫が家事をしないのは、やる気がないからではなく、「気づいていない」か「文句を言われて反発したくなってしまう」。そんなすれ違いが根っこにあるのかもしれません。
伝え方や仕組みをほんの少し変えるだけで、そのズレは「分担」へと変わっていきます。

「今、家事をしてくれなくて苦しい…」そんな毎日も、今日のひと言や小さな工夫で、少しずつ変わり始めるかもしれません。