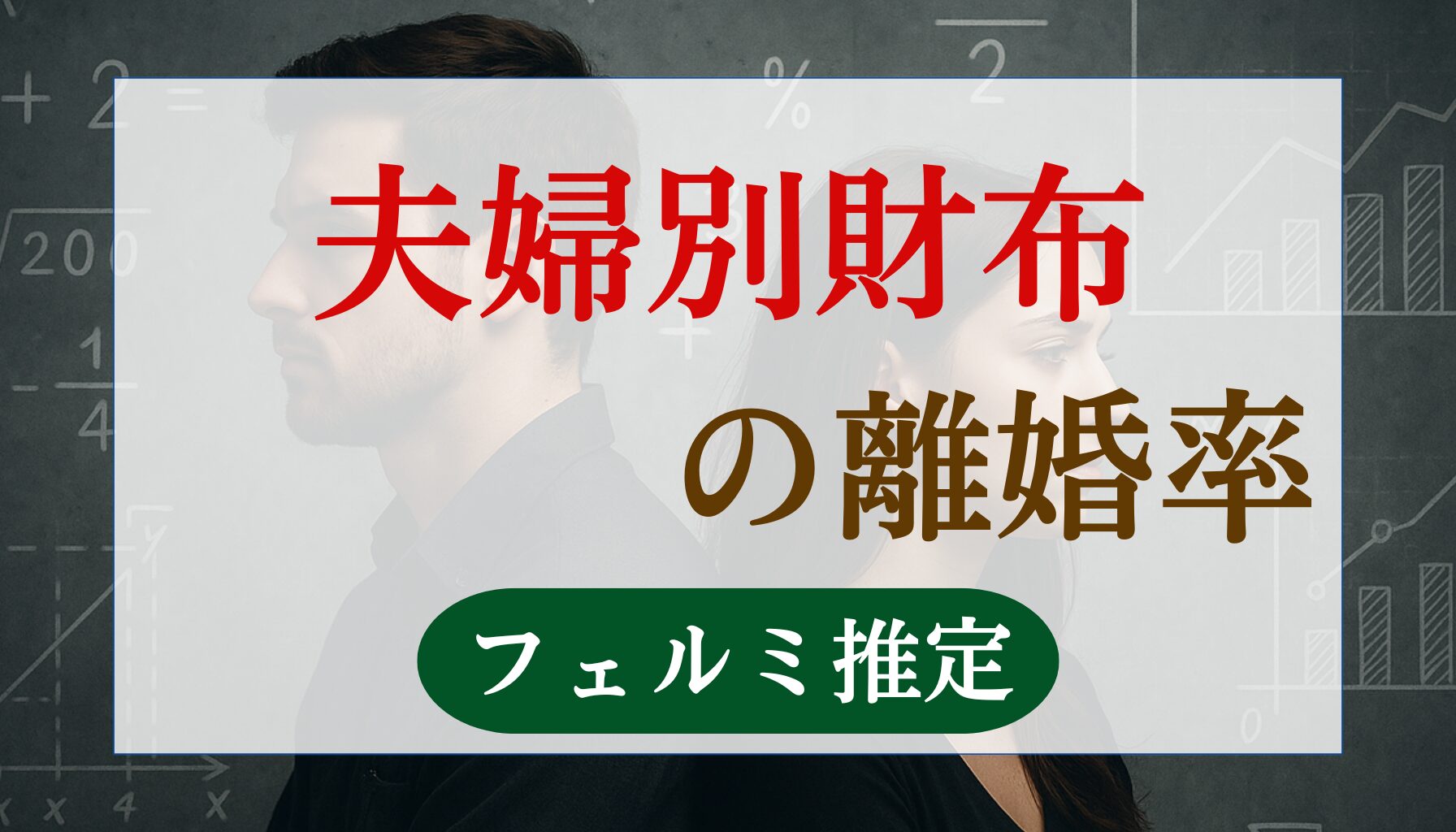夫婦別財布世帯の離婚率、実は0.129/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約8.8%。年離婚確率で見ると、なんと全国平均の約1.4倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
夫婦別財布の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①夫婦別財布とは?対象となる夫婦の定義
ここでは、「夫婦別財布」を「夫婦それぞれが別の口座や収入単位でお金を管理しているスタイル」と定義します。
このうち、実際に「別財布」で暮らしている世帯はどれくらいか見ていきましょう。
②日本における夫婦別財布の割合を推定してみた
複数の調査結果を見ると、夫婦別財布の割合にはばらつきがあります。
- マネーフォワード調査(2014年):別口座管理 43%
- サンケイリビング調査(2017年):完全別会計 17.3%
- 日本経済新聞(2023年):30代共働き層で別財布 61%
以上をふまえて、全体に占める割合は 保守的に20%と仮定します。
2,735万組 × 0.20 = 約 547万組
つまり、日本にはおよそ 547万組の夫婦別財布世帯 がいると推定できます。
③調査データと仮定から見る年間離婚確率と件数
国立社会保障・人口問題研究所(2018年)の調査によると、夫婦別財布世帯の離婚経験率(累積)は 2.3% でした。
これを10年での離婚率とし、年あたりの離婚確率に直してみます。
年次離婚確率 = 1 − (1 − 0.023)^(1/10) ≒ 0.00233(=0.233%/年)
この確率を使って、年間の離婚件数を出します。
547万組 × 0.233% ≒ 12,755組/年
つまり、夫婦別財布世帯の中で、年間に離婚するのは およそ12,755組 ということになります。
④全国平均と比べて高い?低い?気になる離婚率の差
推定によると、夫婦別財布層の離婚は年間でおよそ 12,755件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
12,755 ÷ 125,000,000 × 1,000 ≒ 0.102/1,000人
一方、全国全体の年間離婚率は 1.52/1,000人 です。
つまり、夫婦別財布層の離婚率は、全国平均の 約6.7% にあたるんですね。
また、年間12,755件という離婚件数は、1日あたりに換算すると…
12,755 ÷ 365 ≒ 約35組/日

これは、毎日約 35組の「夫婦別財布」カップル が離婚していることになるんです。
SNSと検索データから見えた「夫婦別財布離婚」の現実
①「育休中も折半!?」SNSで噴出するリアルな声
SNS上で「夫婦別財布」にまつわる800件以上の投稿を分析してみました。
その中で、ネガティブな内容は375件(46.9%)と、もっとも多くを占めています。
投稿の内容を見てみると、「育休中なのに生活費も割り勘」「出産費用は私が全額負担」「病気のときも家計の支援がなかった」など、切実な声が多くありました。
とくに多かったのは、出産・育児といったライフイベントの負担が共有されないことへの不満です。
実際、「育休・出産と財布別の限界」に分類された投稿は、全体の中でも最多の84件にのぼりました。
この傾向を受けて、SNS上の感情を反映する補正として、高めの補正係数1.15を設定しました。
②Googleトレンドでわかる関心層と地域の偏り
Googleトレンドを使った分析では、「夫婦別財布」への関心は2016年以降ずっと続いています。
注目すべきは、地域ごとの検索傾向です。
もっとも検索スコアが高かったのは徳島県。
続いて栃木県、高知県、香川県、石川県など、地方圏が上位を占めていました。
こうした地方では、「お金の使い方をはっきりさせたい」とか、「周りに合わせなきゃという雰囲気が強いことが影響しているのかもしれません。
地方に偏りがある傾向をふまえ、検索関心による補正係数は 控えめに1.10倍 に設定しました。
③SNSと検索を掛け合わせて見えた別財布夫婦のすれ違い
ここまでで設定したSNS補正係数1.15と、検索トレンド補正係数1.10を掛け合わせます。
1.15 × 1.10 = 1.265
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:12,755件 × 1.265 ≒ 16,135件
年間離婚確率:16,135 ÷ 5,470,000 ≒ 0.295%/年
離婚率:16,135 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.129/1000人
そして、1日あたりに直すと…
16,135 ÷ 365 ≒ 約44組/日
つまり、毎日およそ 44組の夫婦 が、夫婦別財布の影響で離婚に至っているということですね。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件の およそ8.8% にあたります。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、夫婦別財布層は 約1.4倍の離婚リスク があるんです。
今後、夫婦別財布層の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
①離婚確率が下がる?改善シナリオとその根拠
まずは、育児や生活費の負担を話し合える「家計会議」の習慣が広まり、企業や自治体が共働き家庭向けの支援制度を充実させ、別財布でも支え合える夫婦の在り方が社会に浸透していった未来を想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率0.295%から、毎年0.01ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.295% − (0.01 × 10) = 0.195%
この0.195%の離婚確率を、該当する夫婦別財布層の世帯数(547万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:547万組 × 0.195% ≒ 10,647件/年
離婚率:10,647 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.085/1000人
1日あたりで見れば、約29件/日。
ここで注目したいのは、現在の補正後数値(16,135件/年)から約5,488件もの離婚が削減できるということです。
つまり、1日あたり約15組の夫婦が離婚を回避できる計算になります。

夫婦別財布でも、支え合う工夫が浸透すれば、こんな穏やかな10年後もあり得るんです。
②離婚率0.5%時代へ?放置すれば進む悪化パターン
一方、生活費の分担にモヤモヤを抱えたまま話し合いもできず、育休や病気のときも「自分の財布でなんとかして」と言われ、お金のことをきっかけに、心の距離まで離れていく未来はどうなるでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.02ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.295% + (0.02 × 10) = 0.495%
この0.495%の離婚確率を、同じく該当する夫婦別財布層(547万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:547万組 × 0.495% ≒ 27,077件/年
離婚率:27,077 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.217/1000人
1日あたりでは、約74件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の補正後数値(16,135件/年)と比較すると、1年で約10,942件も多くなり、10年で10万件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べても、0.495%は約74%を占めるまで拡大。

見て見ぬふりを続けることで、家計の仕組みが信頼関係を壊すきっかけになってしまう。そんな未来もありえるんです。
③「夫婦でどう向き合うか」で10年後が変わる?今日から変われる小さな工夫
ポジティブな未来(0.195%)とネガティブな未来(0.495%)を比べると、たった10年で約0.3ポイント=2.5倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.085/1000人 vs 0.217/1000人。
年間離婚件数では10,647件と27,077件という、なんと16,430件もの違いが生まれます。
この差は、「財布の管理方法が、信頼関係にも影響する」という現実を表しています。
実際にネット上では、「ちょっとした工夫で関係がやわらいだ」「夫婦の話し合いが増えた」といった声も多く見られます。
- 家計会議の定例化
ある家庭では「月初に家計報告と生活の振り返りをセットで行う日」を設けています。 お金の話に限らず、相手への感謝や困っていることも口にする時間にしており、単なる数字の確認にとどまらない夫婦の対話の場となっているそうです。 - 支出ごとの担当制を導入する
「折半ではギスギスする」と感じた夫婦が、食費・住居費・教育費などの項目を分担する形式に切り替えた例があります。 担当制により、相手にお願いするストレスが減り、家計の話も建設的になったとの声がありました。 - 「貯金だけは共通化」するルール
それぞれ財布は別でも、「将来の安心のために積み立てる貯金」は共通口座に毎月定額で入れるという家庭もあります。 日々の使い道は自由を保ちつつ、将来への約束を一緒にしている感覚が心の支えになるそうです。 - サブスク・固定費は片方が全額持つ取り決め
ネット上には、「Netflixやスマホ代、電気代などの定額系は夫」「食費・日用品は妻」など、生活費の性質に応じて役割を分けている家庭もあります。 一律の折半より実生活に合い、感謝が生まれやすいとの意見が見られました。 - 家計にまつわるありがとうを見える化する
「支払ってもらって当然」という空気が苦手だったという投稿者は、支出に対して必ずありがとうの言葉かLINEスタンプを送るルールを決めたそうです。 小さなやりとりでも、気持ちの摩耗を防ぐ効果があったと語っていました。 - 一緒にお金の勉強をする時間をつくる
「ふるさと納税」「NISA」「教育費の平均」など、家計にまつわることを月1で夫婦一緒に調べる時間を作っているという家庭もあります。 金銭感覚や情報のギャップが埋まり、相手の見えない努力にも気づけるようになったとのことです。

財布が別でも、心はひとつになれる。 大切なのは、仕組みよりも「思いやりの積み重ね」。 今日の小さな行動が、10年後のふたりを穏やかに変えてくれます。