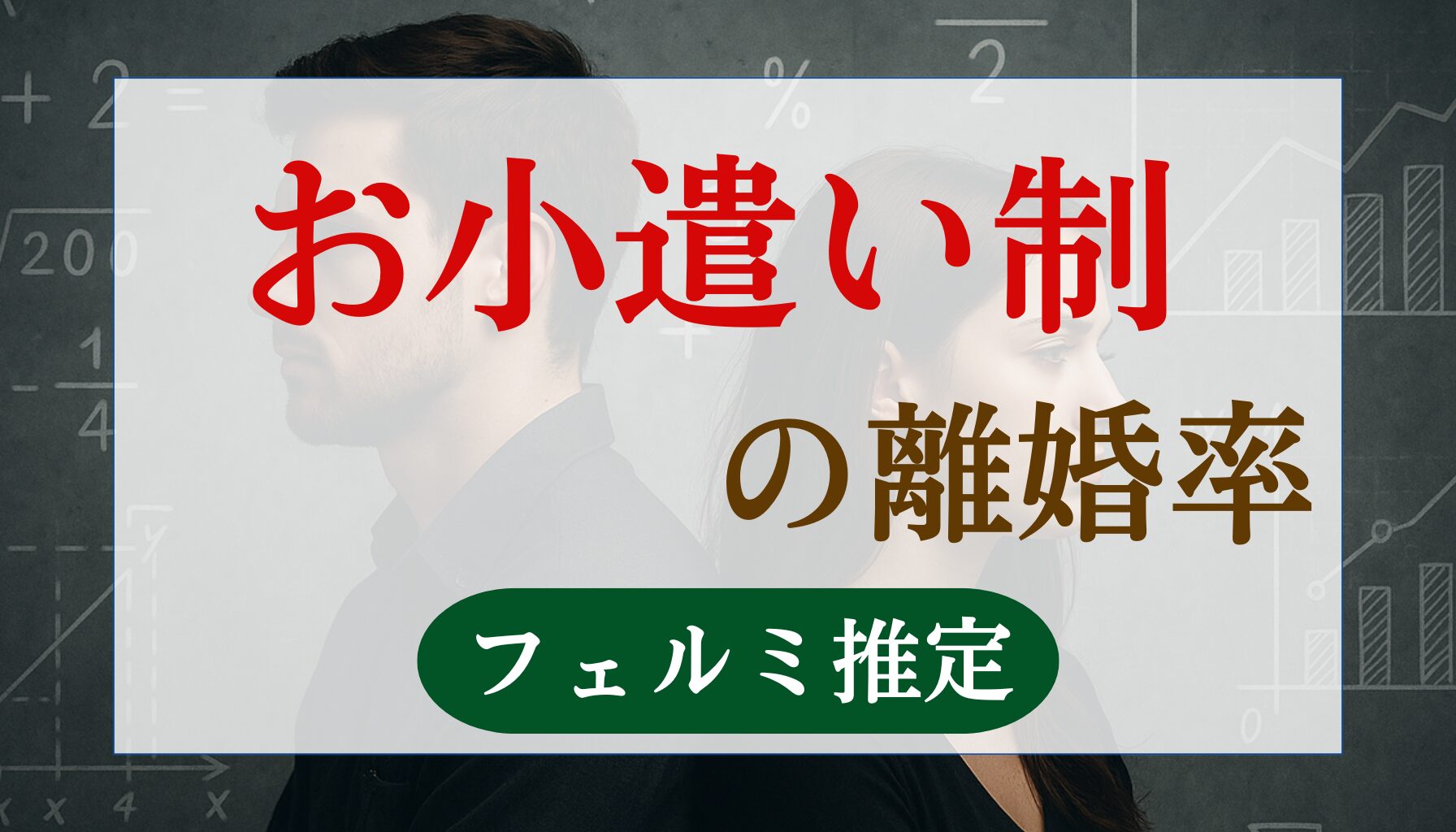お小遣い制夫婦の離婚率、実は0.73/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約49.4%。年離婚確率で見ると、全国平均とほぼ同水準なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
お小遣い制夫婦の離婚率をフェルミ推定してみた【独自分析】
①「お小遣い制」とは?対象となる夫婦を定義
「お小遣い制」は、家計を夫婦のどちらか一方が握り、もう一方が決められた金額を毎月受け取るという仕組みです。
日本では、夫が働き、妻が家計を管理し、その中から夫にお小遣いを渡すケースが多く見られます。
ここでは、「どちらかが家計を管理し、パートナーに毎月一定額を手渡す形」を「お小遣い制世帯」と定義しました。
②全国の既婚家庭における「お小遣い制」の割合を推定
日本には、約2,735万組の既婚カップルがいます(出典:厚生労働省『国民生活基礎調査2023』)。
このうち、Clamppyの調査(2025年)によると、「現在お小遣い制」は43.6%、「過去に経験あり」は8.6%とされています。
また、新生銀行の長年の調査でも、「妻管理型のお小遣い制」が4〜5割という傾向が続いているんです。
こうした調査結果をもとに、お小遣い制世帯の割合をおおよそ50%と仮定すると、全国で約1,370万組が該当することになります。
③調査結果と仮定に基づいた年間離婚確率と件数
お小遣い制の家庭では「不満がたまりやすい」「対話が不足しがち」「自由が制限される」などのストレスが溜まりやすいことが指摘されています。
実際、法務省の「離婚理由統計」によると、妻側の離婚理由の第2位が「生活費を渡さない」。
これは経済面での不満を表していると言えるでしょう。
また、新生銀行やClamppyの調査でも、「夫側が自由に使えるお金が少なく、心理的負担を感じる」といった声が多く寄せられています。
こうした状況をふまえ、お小遣い制家庭の離婚確率は、全国平均の1.2倍と仮定します。
0.67%(日本の年間離婚確率) × 1.2 = 0.80%
この確率を、お小遣い制世帯1,370万組にあてはめると...
1,370万組 × 0.0080=109,600組
④「お小遣い制夫婦の離婚率」と全国平均の比較結果
推定によると、お小遣い制世帯の離婚は年間でおよそ109,600件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
109,600 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.88/1000人
一方、全国全体の年間離婚率は1.52/1000人です。
つまり、お小遣い制家庭の離婚率は、全国平均のおよそ58%にあたります。
また、年間109,600件という件数は、1日あたりに換算すると約300組。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、お小遣い制家庭の離婚確率は0.80%で、約1.2倍のリスクがあるんです。
ただし、ここまでの推計はあくまで統計データをもとにした数字です。
次は、SNSの投稿や検索行動から、より実態に近い数値を出していきましょう。
SNSと検索データから見えたお小遣い制夫婦の葛藤と現実
①「制限されている感覚」が反発を生む?SNSでの声
SNS上の「お小遣い制」に関する471件の投稿を分析したところ、ネガティブ208件、ポジティブ168件、中立95件で、全体として否定的な反応がやや多めでした。
特に目立ったのは、制度そのものへの不満ではなく、「自分で稼いだのに自由に使えない」「一方的に管理されて尊厳が傷つく」といった、「扱われ方への反発」です。
こうした拒否感の多くは、「信頼されていない」「話し合いがない」と感じることによる心理的な負担から生まれているようです。
一方で、ポジティブな投稿では「貯金や投資に役立った」「夫婦でしっかり相談して取り入れた」といった、話し合いを前提にした使い方が評価されていました。
つまり、「制度」というよりも「どのように話し合って決めたか」によって意見が大きく分かれるのが特徴です。
そのため、全体としてはネガティブ傾向ではありますが高リスクとまでは言えないため、補正係数はやや控えめに0.883に設定しました。
②Googleトレンドが示す「お小遣い制」への関心と地域性
Googleトレンドによると、「お小遣い制」という検索は2011年以降ずっと高水準で推移しており、一時的な流行ではなく家庭内の制度として定着していることがうかがえます。
検索の関心が特に高かったのは、岡山県・岩手県・熊本県・山梨県などの地方圏。
これらの地域では、専業主婦世帯の比率が全国平均より高く、伝統的な家族観が残りやすい傾向があります(参考:内閣府 男女共同参画白書 2021)。
そのため、「夫は働き、妻が家計を握る」という構図が続きやすい地域では、家庭内の力関係にも影響が出やすいと考えられるでしょう。
ただし、「不満」や「離婚」といったネガティブなワードの検索は限定的であり、検索の高さがそのまま離婚リスクに直結するわけではありません。
こうした点をふまえ、検索データに基づく補正係数は、やや低めに0.94と設定しました。
③数字と感情が交差する、お小遣い制夫婦の見えないストレス
ここまでで設定したSNS補正係数0.883と、検索トレンド補正係数0.94を掛け合わせます。
0.883 × 0.94 = 0.829
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:109,600件 × 0.829 ≒ 約90,840件
年間離婚確率:90,840 ÷ 1,370万組 ≒ 約0.66%/年
離婚率:90,840 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.73/1000人
そして、1日あたりに直すと…
90,840 ÷ 365 ≒ 約249組/日
つまり、毎日およそ249組の夫婦が、「お小遣い制」をきっかけに離婚に至っているということですね。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件のおよそ49.4%にあたります。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、お小遣い制家庭の離婚確率は約0.66%で、ほとんど同じくらいの確率なんです。
今後お小遣い制家庭の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
① 離婚件数が3割減?夫婦の対話が当たり前になるポジティブな未来
まずは、家計の「見える化」やお小遣いに関する夫婦間の話し合いが当たり前になる、前向きな未来から想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率0.664%から、毎年0.02ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には...
0.664% − (0.02 × 10) = 0.464%
この0.464%の離婚確率を、該当するお小遣い制世帯数(1,370万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:1,370万組 × 0.464% ≒ 63,500件/年
離婚率:63,500 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.508/1000人
1日あたりで見れば、約174件/日。
ここで注目したいのは、現在の数値(90,840件/年)から約27,340件もの離婚が削減できるということです。
つまり、1日あたりにすると、約75組の夫婦が離婚を回避できる計算になります。

お小遣い制が話し合って活用されるようになれば、夫婦の不満もグッと減らせるはずです。
② 離婚確率0.9%超に上昇?対話不足による悪化シナリオ
一方、家庭内の金銭管理が「一方通行の押し付け」のまま不満が溜まっていく、そんな状況が続いたとしたらどうなるでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.03ポイントずつ上昇すると仮定します。
すると、10年後には...
0.664% + (0.03 × 10) = 0.964%
この0.964%の離婚確率を、同じくお小遣い制世帯(1,370万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:1,370万組 × 0.964% ≒ 131,900件/年
離婚率:131,900 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 1.055/1000人
1日あたりでは、約361件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の補正後数値(90,840件/年)と比較すると、1年で約41,060件も多くなり、10年で40万件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、0.964%は約1.44倍に相当します。

「話し合い」という大切な一歩がなければ、お金のストレスが夫婦関係をむしばんでいく未来もあり得るんです。
③ 10年後に何が変わる?私たちが今できる対策
ポジティブな未来(0.464%)とネガティブな未来(0.964%)を比べると、たった10年で0.5ポイント=約2.1倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.508/1000人 vs 1.055/1000人。
年間離婚件数では63,500件と131,900件という、なんと約68,400件もの違いが生まれます。
「お小遣い」が夫婦にとって信頼や自由を実感できる仕組みになるのか、それとも関係をこじらせるきっかけになるのかで、大きな分かれ道になるんです。
実際にネット上では、お小遣い制ならではの悩みに対して、こんな工夫をしている家庭がありました。
- 家計の見える化で対話の土台をつくる
ある家庭では、お小遣いの金額をめぐって衝突が続いていました。そこで家計簿アプリを使って、毎月の支出や余剰金を一緒に見える化してみたそうです。すると、「なぜこの金額なのか」が冷静に話せるようになり、夫婦の納得度もぐっと高まったといいます。 - お金の使い道を具体的に共有する習慣をもつ
「月2万円で何をしたいのか」を具体的に伝えるようにしたことで、相手の理解が深まったという声がありました。「趣味」や「飲み会」といったざっくりした言い方ではなく、「付き合いの会食1回・書籍・散髪代」といった細かい説明にすることで、誤解も少なくなったそうです。 - 0円小遣いや1万円未満なら分担の再交渉を
月1万円未満の小遣いで、「昼食・通勤・交際費」までまかなっている家庭も。ある家庭では、妻が趣味に月3万円かけていたことを知り、夫が初めて家計の見直しを求めたというケースがありました。生活費の分担に不公平感があるなら、一度しっかり話し合ってみることが大切です。 - お小遣いの中身を項目別に仕分けておく
ある家庭では、「昼食・散髪・被服費」は家計から、それ以外は小遣いからという分け方に変えてみました。すると、同じ月2万円でもお金の自由度が全然違って感じられ、夫婦の納得感がずいぶん上がったそうです。 - 労働時間のバランスで議論する
「週2日のパートなのに、家計のすべてを握られている」と悩む人も。実際の労働時間や家計への貢献度を比べながら、お金の使い方に関する自由度も話し合ってみたという家庭もあります。金額の多い・少ないだけでなく、「誰がどれだけ頑張っていて、どこまで自由に使えるのか?」を一緒に考えることで、モヤモヤが解消されたとのこと。 - お金の価値観にズレを感じたら、話し合いの場を確保する
「お小遣い=ATM扱いされているように感じる」といった声も多く見られました。そんなときは、月1回だけでも「お互いの価値観を言葉にする時間を設けた」という家庭もあります。こういった話し合いにより、金額の問題ではなく、「どう扱われているか」にこそ不満があると気づけることもあるんです。
お小遣いは、単なるお金ではなく、「信頼」や「自由度」を表すものなのかもしれません。
どちらかがずっと我慢しているような関係では、その小さな不満がやがて大きな亀裂につながってしまいます。

だからこそ金額の大小だけでなく、「なぜその金額なのか」「どうすれば納得できるのか」を一緒に話し合うことが大切ですよ。