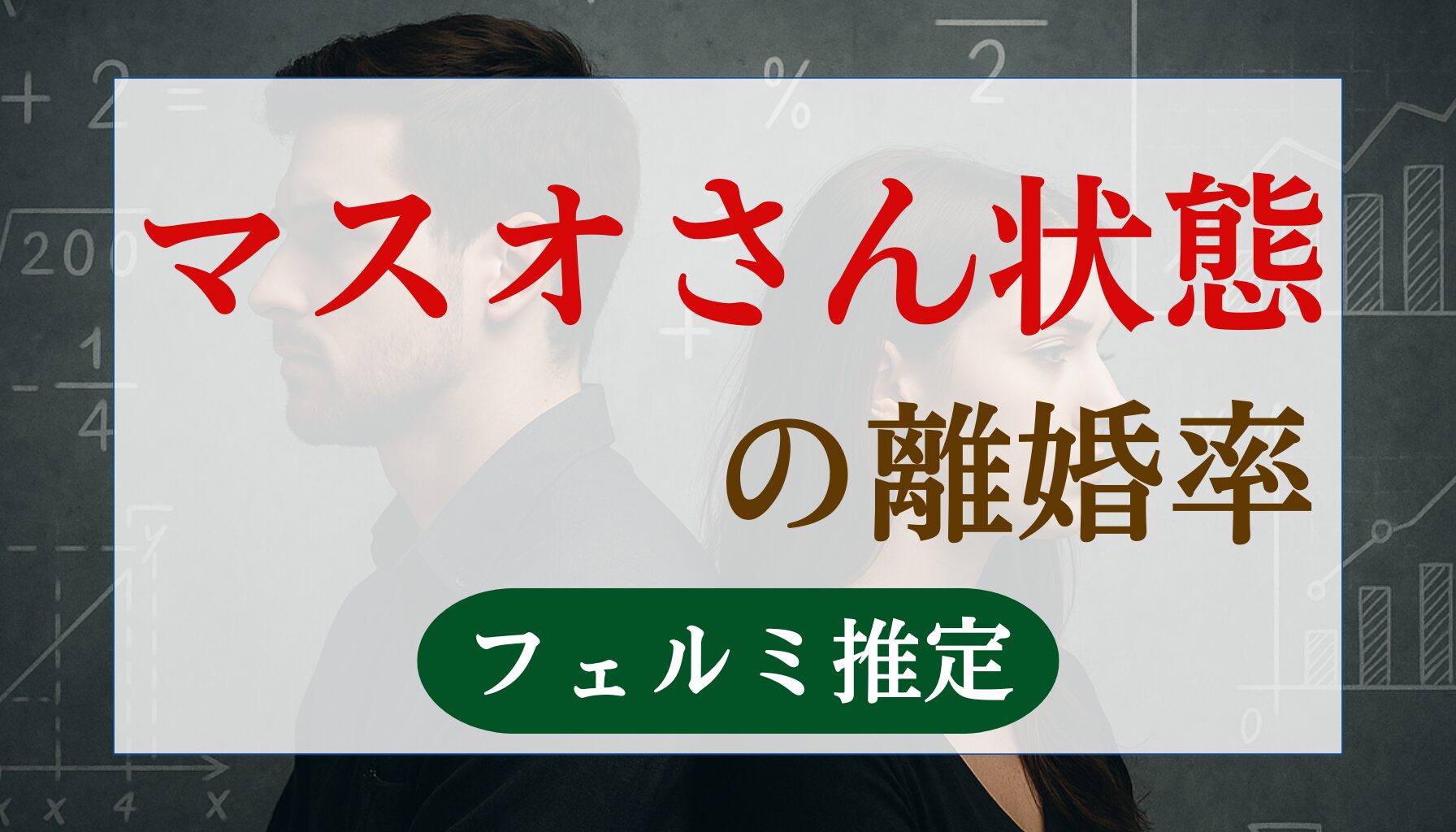マスオさん状態の離婚率、実は0.084/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約5.7%。年離婚確率で見ると、なんと全国平均の約1.14倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
マスオさん状態の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①マスオさん状態とは?どんな夫婦が対象になるのか
「マスオさん状態」とは、夫が妻の親と一緒に暮らしている夫婦のことを指します。
名前の由来は、国民的アニメ『サザエさん』に登場するマスオさん。
妻サザエの家族と同居している設定から、この言葉が広まりました。
このマスオさん状態にある夫婦が、どのくらい離婚しやすいのか、数値を使って具体的に見ていきましょう。
②マスオさん状態の夫婦はどれくらいいる?割合を推定
まず、日本にいる既婚カップルの総数は、約2,735万組とされています(出典:厚生労働省『国民生活基礎調査 2023』)。
その中で「妻の親と同居している」夫婦の割合は、およそ5.0%(出典:国立社会保障・人口問題研究所『第7回全国家庭動向調査 2022』)。
つまり、マスオさん状態の夫婦数はこうなります。
2,735万組 × 5.0% = 約136.8万組(=1,367,500組)
③調査データと仮定から導くマスオさん状態の年間離婚確率と件数
「マスオさん状態」の離婚のしやすさについては、研究によって見解が分かれています。
たとえば、全国家族調査(2005年)では、夫の親と同居すると離婚は抑えられる傾向が見られましたが、妻の親との同居では明確な傾向は出ていません。
一方、IUSSP(2013年)では、夫の親と同居する夫婦は、離れて暮らす夫婦より離婚リスクが66%も低いという報告があります。
さらに、慶應義塾大学(2018年)の研究では、妻の親と同居する夫婦は、むしろ離婚が多くなるというデータも出ています。
このようにデータが相反しているため、今回は全国平均の1.15倍の離婚確率という保守的な仮定をしました。
これを全国の年間離婚確率(0.67%)に当てはめると、
0.67% × 1.15 = 0.77%/年
この確率を、先ほどのマスオさん状態の夫婦数(1,367,500組)に掛けると…
1,367,500 × 0.77% ≒ 約10,537組/年
④全国平均と比べてどれくらい高い?マスオさん状態の離婚率
推定によると、マスオさん状態の離婚は年間でおよそ10,537件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
10,537 ÷ 125,000,000 × 1,000 ≒ 0.084/1000人
一方、日本全体の年間離婚率は1.52/1000人です。
つまり、マスオさん状態の離婚率は、全国平均の5.5%を占めているんですね。
また、年間10,537件という離婚件数は、1日あたりに換算するとおよそ29組の夫婦が離婚している計算になります。
ただし、ここまでの推計はあくまで統計データをもとにした数字です。
次は、SNSの投稿や検索行動から、より実態に近い数値を出していきましょう。
SNSと検索データから見えたマスオさん状態と離婚の実態
①SNS投稿から見えたマスオさんからの「つらい」「やってられない」の声
SNSで「マスオさん状態」に関する投稿を分析すると、ポジティブ96件、ネガティブ114件、中立501件でした。
ネガティブな投稿には「義実家との衝突」「お小遣い制」「無一文」など深刻なテーマが多め。
たとえば、「姑が天敵で無一文で追い出された」「休みの日は掃除を命じられて体調を崩した」など、精神的にも体力的にもギリギリな生活が綴られていました。
また、「収入を全額管理されていて、お小遣いは月5万円だけ」という声もあり、経済面での自立のしづらさや、夫婦間の力関係の偏りがうかがえます。
一方で、「育児中にすごく助かった」「夫が同居してくれて感謝している」といったポジティブな声もあり、必ずしも「同居=不幸」というわけではありません。
ただ、全体を通してみると、やはりストレスやモヤモヤのほうが多く語られていました。
そこで、SNSの傾向をふまえた補正として、やや高めに1.0143という係数を設定しました。
②Googleトレンドから読み解くマスオさん状態への関心の波
「マスオさん状態」というキーワードは、それほど多く検索されているわけではありません。
2010年末に一度だけ大きな検索の波が見られましたが、その後は時折思い出したように検索されるニッチな関心といえそうです。
注目すべきは地域別の傾向で、山形・高知・新潟・福島・福井など、地方圏での関心が比較的高いという点。
これは、地域的に同居が当たり前の文化があったり、住宅の構造が同居を前提にしているケースがあるためかもしれません。
ただし、検索の持続性は低く、長期的な問題というより、特定の場所で突発的に気になる話題という性質が強いです。
そのため、Google検索の結果に基づく補正係数は、やや低めに0.98と設定しました。
③SNSと検索を掛け合わせて見えた現実とすれ違い
ここまでで設定したSNS補正係数1.0143と、検索トレンド補正係数0.98を掛け合わせます。
1.0143 × 0.98 = 0.994014
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:10,537件 × 0.994014 ≒ 10,471件
年間離婚確率:10,471 ÷ 1,367,500(対象テーマ夫婦の数) ≒ 約0.765%/年
離婚率:10,471 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.084/1000人
そして、1日あたりに直すと…
10,471 ÷ 365 ≒ 約29組/日
つまり、毎日およそ29組の夫婦が、マスオさん状態から離婚に至っているということですね。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件のおよそ5.7%にあたります。

さらに、既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、マスオさん状態の夫婦は約1.14倍の離婚リスクを抱えていることになります。
今後マスオさん状態の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
①離婚件数が2/3減?家族意識が強まった場合のポジティブ未来
たとえば、「夫は家族の外の人」みたいなよそよそしさがなくなって、妻は親ばかりではなく夫との関係も大切にする。そして、夫も遠慮せずに家族の一員として関われる、そんなあたたかい家族の形を築くことが当たり前になった未来を想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率0.765%から、毎年0.05ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.765% − (0.05 × 10) = 0.265%
この0.265%の離婚確率を、該当するマスオさん状態の夫婦数(136.75万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:1,367,500組 × 0.00265 = 約3,623件/年
離婚率:3,623 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.029/1000人
1日あたりで見れば、約10件/日。
ここで注目したいのは、現在の数値(10,471件/年)から、約6,848件もの離婚が削減できるということ。
つまり、1日あたり約19組の夫婦が、離婚を回避できる計算になります。

義実家との関係や家族内のルールをほんの少し意識するだけで、離れずにすむ家族がぐっと増えるんです。
②離婚確率が1.2%超に?誰にも相談できない状況が続いた場合の悪化シナリオ
もし、「夫はずっと遠慮していて、家の中で居場所がないまま。妻は親にばかり頼って、夫婦の会話もどんどん減っていく。気づけば、同じ家にいても心はバラバラ...そんなすれ違いが続いていったらどうでしょう。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.05ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.765% + (0.05 × 10) = 1.265%
この1.265%の離婚確率を、同じく該当するマスオさん状態の夫婦数(136.75万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:1,367,500組 × 0.01265 = 約17,304件/年
離婚率:17,304 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.138/1000人
1日あたりでは、約47件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の補正後数値(10,471件/年)と比較すると、1年で約6,833件も多くなり、10年で68,000件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、1.265%は約1.9倍に相当します。

お互いを家族として迎え合う姿勢がないと、一緒にいるのに孤独という状況にいつの間にか陥ってしまうかもしれません。
③10年後の差はどれだけ広がる?今できる対策と行動
ポジティブな未来(0.265%)とネガティブな未来(1.265%)を比べると、たった10年で約1ポイント=約4.8倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.029/1000人 vs 0.138/1000人
年間離婚件数では3,623件と17,304件という、なんと13,681件もの違いが生まれます。
ネット上では、以下のような対策をしているマスオさん状態夫婦の声もが見られました。
- 「娘モード」ではなく「妻モード」に切り替える意識
同居生活が長くなると、妻が娘としての顔ばかりになり、夫婦としての時間がなくなることも。ある家庭では「せめて寝る前だけは、夫婦の会話だけにする時間をつくる」と決めたことで、夫婦関係が少しずつ回復していったそうです。 - 旅行・イベントは家族単位でリハーサルする
義実家との旅行に疲弊していた夫が、「まずは自分と妻・子供の3人だけの旅行」を提案。
結果的に妻も気兼ねない時間の大切さを理解し、義実家との付き合い方も自然に見直されたそうです。 - 義実家との会話は母娘だけで完結させない
ある家庭では、義実家との同居中に妻とその母親だけで話を進めがちになっていたそうです。結果的に夫が疎外感を覚え、ストレスが蓄積されたとのこと。「母娘で決めないで、夫にも一声かけてから話を進める」というルールを設けたことで、関係が穏やかになっていったといいます。 - 夫婦というチームとして向き合う
「ケンカになると、妻はすぐ親の味方をする」そんな悩みを抱えた夫の投稿がありました。大切なのは、妻が親の娘としてではなく、夫のパートナーとして向き合える関係を作ること。まずは感情に流されず、公平な目で二人でちゃんと話し合うことが大切です。 - 妻が夫を気遣いフォローする
ある家庭では、義母が夫に対して強い言い方をしたとき、妻がその場で話題を変えたり、あとで「ごめんね、ちょっと言いすぎだったよね」とフォローするようにしたそうです。それだけで夫は「ちゃんと見てくれている」と感じ、義実家との関係にも前向きになれたとのこと。親と夫の間に立つ妻のちょっとした気づかいが夫の支えになります。 - 義両親を敵にしない伝え方を意識する
ある投稿では、「義両親を責めた途端に、妻が完全にシャットアウトしてくる」との声がありました。義両親の言動に不満があっても、共通の課題として話すスタンスが大事。「みんなが気持ちよく暮らすにはどうしたらいいか」という考え方で、夫婦の対話が建設的になったという事例もありました。
マスオさん状態は、気づかないうちに夫が家族の中で孤立しやすいと状況と言えるでしょう。
でも、妻のちょっとした気づかいや夫婦で家族の形についてしっかり話し合うことで、関係性は変わっていきます。

10年後の家族がどうなっているかは、「今、お互いをちゃんと家族として大切にできているか」で決まるのかもしれません。