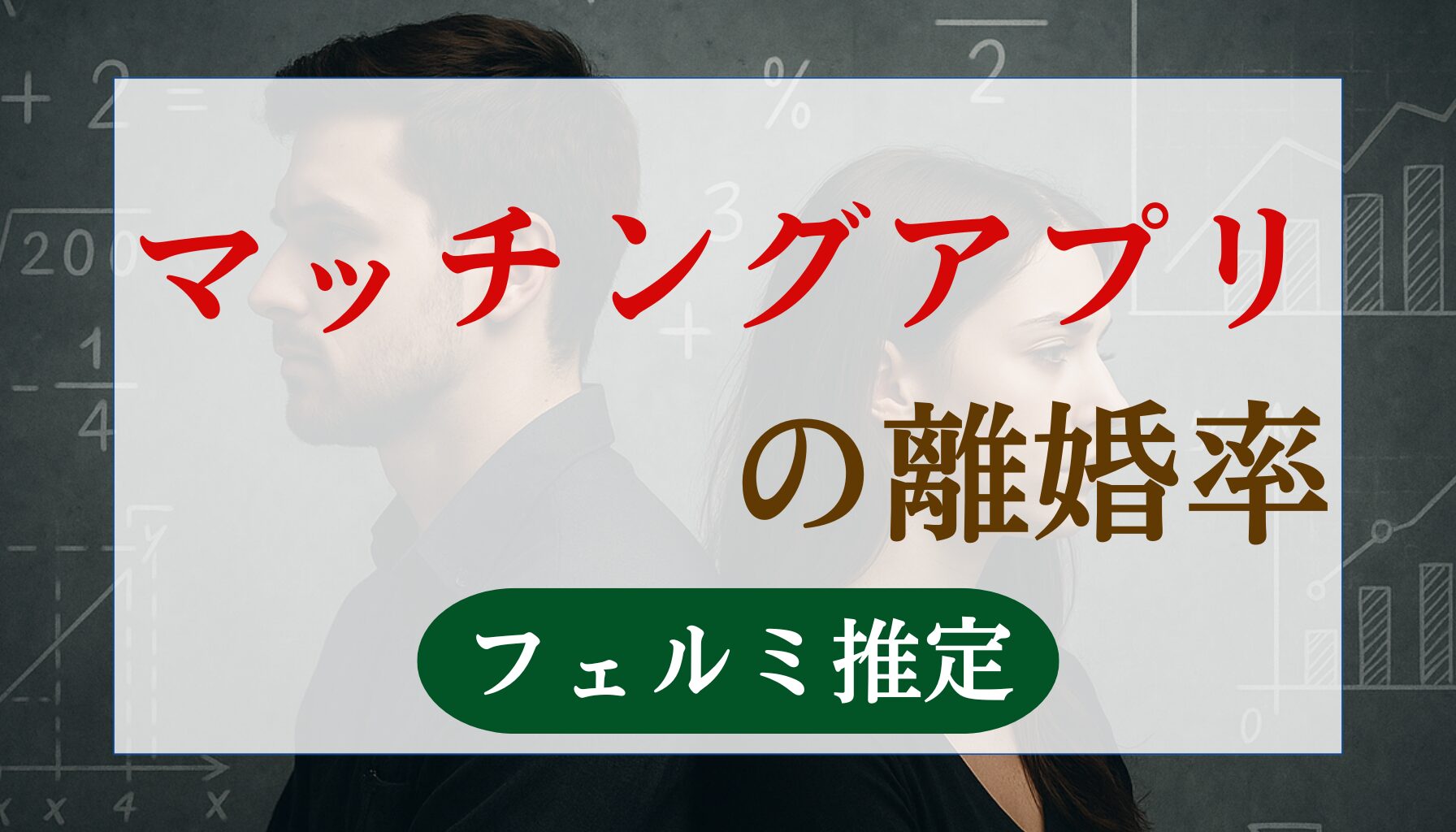マッチングアプリ婚の離婚率、実は0.020/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約1.4%。年離婚確率で見ると、全国平均の約0.91倍でやや低めなんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
マッチングアプリ婚の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①マッチングアプリ婚とは?対象となる夫婦の定義
ここでいう「マッチングアプリ婚」とは、マッチングアプリやオンラインサービスで出会い、結婚に至ったカップルのことです。
推定には、国立社会保障・人口問題研究所が2021年に行った「過去6年以内に結婚した夫婦」を対象にした調査データを参考にします。
つまり、「過去6年以内にオンラインで出会って結婚した夫婦」が今回の対象です。
②全体の中でどれくらい?マッチングアプリ婚の割合を推定
まずは、日本の既婚カップル全体のうち、マッチングアプリ婚がどれくらいの割合なのかを見ていきましょう。
国立社会保障・人口問題研究所(2021年)によると、過去6年以内に結婚した夫婦で、「ネット(アプリ含む)で出会った」人たちは13.6%という調査結果があります。
次に、日本の年間婚姻数は約50万組です。
それを踏まえると、過去6年間に結婚したカップルは、
約50万組 × 6年=300万組
日本の既婚カップルは約2,735万組なので、300万組は全体の約11%の割合です。
さらに、過去6年以内に結婚した夫婦で、ネット(アプリ含む)で出会った人の割合は...
0.11 × 0.136 = 0.01496 → 約1.5%
これを夫婦数に置き換えると、
2,735万組 × 1.5% = 40.9 万組
つまり、現在の日本ではマッチングアプリ婚のカップルは約40.9万組いると推定できます。
③年間でどのくらい離婚している?仮定に基づく離婚確率と件数
では、約40.9万組のアプリ婚のうち、年間でどのくらいのカップルが離婚しているのでしょうか?
ここでは、累積離婚率を年単位に換算する方法で、離婚確率を割り出します。
2020年、毎日放送『日曜日の初耳学』が実施した調査によると、アプリ婚の累積離婚率は4.5%でした。
この数値を仮の結婚年数で割ってみると、以下のようになります。
・5年換算 → 0.92%/年
・7年換算 → 0.66%/年
・10年換算 → 0.46%/年
今回はこの中間値をとって、年間離婚確率を0.60%と設定します。
これを、マッチングアプリ婚の夫婦数に当てはめると...
40.9万組 × 0.60% = 約2,470組/年
④全国平均と比べて高い?低い?マッチングアプリ婚の離婚率比較
推定によると、マッチングアプリ婚の離婚は年間でおよそ2,470件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
2,470 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.020/1000人
一方、全国全体の年間離婚率は1.52/1000人です。
つまり、アプリ婚の離婚率は、全国平均のおよそ1.3%を占めているんですね。
また、年間2,470件という離婚件数は、1日あたりに換算するとおよそ6.8組の夫婦が離婚している計算。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、「マッチングアプリ婚」層の離婚確率は0.60%。約0.91倍とリスクはやや低めなんです。
ただし、ここまでの推計はあくまで統計データをもとにした数字です。
次は、SNSの投稿や検索行動から、より実態に近い数値を出していきましょう。
SNSと検索トレンドから見えたマッチングアプリ婚と離婚の実態
①SNSでは賛否が拮抗?「幸せ vs 不信感」の声
SNS上で「マッチングアプリ婚」に関する投稿383件を分析してみると、ポジティブ140件、ネガティブ122件(その他は中立的)とほぼ同数でした。
つまり、SNSでは「幸せ」と「不信感」が拮抗している状態です。
たとえば、「生活満足度が高い」「再婚にも前向きになれた」といった声がある一方で、「結婚後もアプリを使っていた」「不倫や詐欺の温床では」といった不安の声も目立ちました 。
こうした状況は、アプリ婚に対して社会全体が慎重に見ていることを反映していると言えそうです。
ただ、全体的にはネガティブ優勢ではなく、離婚リスクが高いとは言い切れないため、SNS補正係数はやや低めに0.92と設定しました。
②「マッチングアプリ 離婚」はなぜ検索される?Googleトレンドの裏にある不安
Googleトレンドで「マッチングアプリ 離婚」というキーワードを調べてみると、2016年ごろから検索数が少しずつ増え、2021年前後にピークを迎えていました 。
これは、アプリ婚が広まり始めた数年後に、離婚や価値観の違いなどのリスクが表面化し始めたことが考えられます。
興味深いのは、検索数が多かった地域。島根・徳島・滋賀・岐阜といった地方県に加え、神奈川のような都市部も含まれていました。
これは、「地方では出会いのチャンスが少ない」「都市部では暮らし方や価値観がバラバラ」といった、出会いから結婚までのすれ違いやすさが背景にあるのかもしれません。
検索数の増加や地域傾向を見ると、「離婚への不安」がじわじわと広がっていることがうかがえます。
そこで、検索の傾向はリスクがやや高いと評価し、1.1というGoogle補正係数を設定しました。
③SNSと検索データを掛け合わせて見えた本当の離婚リスク
ここまでで設定したSNS補正係数0.92と、検索トレンド補正係数1.1を掛け合わせます。
0.92 × 1.1 = 1.012
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:2,470件 × 1.012 ≒ 約2,498件
年間離婚確率:2,498 ÷ 409,000組 ≒ 約0.61%/年
離婚率:2,498 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 約0.020/1000人
そして、1日あたりに直すと…
2,498 ÷ 365 ≒ 約6.8組/日。
つまり、毎日およそ7組の夫婦が、マッチングアプリで出会って結婚した末に、離婚しているという計算です。
また、この件数は、全国の年間離婚件数183,808件のおよそ1.4%にあたります。

さらに、既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べてみると、アプリ婚層の離婚確率は約0.91倍でやや低いということが分かりました。
今後マッチングアプリ婚の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
①離婚件数が2/3に?支援と理解が進んだ場合のポジティブシナリオ
まずは、結婚前に価値観を話し合える仕組みや交際マニュアルなどが整っていて、夫婦もサポート講座やカウンセリングを前向きに取り入れている、そんな明るい未来から想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率0.61%から、毎年0.02ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.61% − (0.02% × 10) = 0.41%
この0.41%の離婚確率を、該当するアプリ婚カップル数(40.9万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:40.9万組 × 0.41% = 約1,677件/年
離婚率:1,677 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.013/1000人
1日あたりで見れば、約4.6件/日。
ここで注目したいのは、現在の数値(2,498件/年)から約821件もの離婚が削減できるということ。
つまり、1日あたり約2.2組の夫婦が離婚を回避できる計算になります。

マッチング・交際後の支援や夫婦間の相互理解がしっかりできていれば、アプリ婚の早すぎる別れはもっと減らせるはずです。
②離婚確率が1.2%に倍増?サポート不足で進む悪化シナリオ
一方で、アプリがどんどんスピード重視になっていく中で、夫婦のほうも価値観をしっかり話し合ったり、サポートを使ったりしないまま結婚してしまう、そんな未来はどうなるでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.03ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
0.61% + (0.03% × 10) = 0.91%
この0.91%の離婚確率を、同じく該当するアプリ婚カップル数(40.9万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:40.9万組 × 0.91% = 約3,722件/年
離婚率:3,722 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.030/1000人
1日あたりでは、約10.2件の離婚が発生する計算です。
また、現在の補正後数値(2,498件/年)と比較すると、1年で約1,224件も多くなり、10年で累計約1万2,240件の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、0.91%は約1.36倍に相当。

対話のないまま「形だけの結婚」が続けば、確率は少しずつ上がってしまうかもしれません。
③10年後の違いと私たちに今できること
ポジティブな未来(0.41%)とネガティブな未来(0.91%)を比べると、たった10年で0.50ポイント=約2.2倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.013/1000人 vs 0.030/1000人。
年間離婚件数では1,677件 vs 3,722件という、なんと約2,045件もの違いが生まれます。
この差を埋めるには、結婚前にしっかりすり合わせをしたり、結婚後も対話を続ける姿勢が重要です。
ネット上では、以下のようなマッチングアプリ婚ならではの工夫が数多く見られました。
- 出会い直後から「価値観マップ」を作成する
ある夫婦は、交際初期から「お金」「家族」「育児」「老後」など10項目にわたってお互いの考えを共有。マッチングアプリでは条件が合っても価値観まで確認しきれないため、見える化することでズレを事前に察知できたといいます。 - 婚姻年数に応じたフェーズ別の課題を話し合う
マチアプ婚は婚姻歴が浅い層が多いため、熟年離婚に関する意識が薄れがちだという声もありました。ある家庭では、1年目・3年目・5年目に「離婚しやすい理由ランキング」を夫婦で共有する機会を設け、未来の地雷を予防しているそう。 - 交際・結婚の流れを振り返る共通史の作成
マチアプ婚の多くは「過去を共有していない」という特徴があります。ある夫婦は、出会いから現在までの共通の年表を一緒に作り、そこにイベント・感情・出来事を見える化。過去の共有によって現在の関係を強化するきっかけになったそうです。 - 離婚に対する意向を事前に確認しておく
ある女性は「離婚観が合わないのが一番怖い」と話していました。そこで、「離婚をどの程度の事態で検討するか」について、結婚前に具体的にシミュレーション。想定のズレを事前に共有することで信頼が深まったとのことです。 - 第三者からの共通の助言役を設定しておく
マッチングアプリ婚では、共通の友人や親族の関係性が希薄な場合が多くあります。ある夫婦は、積極的にお互いの友人や先輩に紹介し合ったそう。「困ったときに話を聞いてもらえる中立役」として依頼し、夫婦間で煮詰まる前に外部相談できる仕組みを作っています。 - 統計やネットの一般論を盲信しすぎない
ネットの投稿でも、「業界の統計トリックに踊らされてるのでは?」という懸念が複数見られました。ある家庭では、夫婦で定期的に「ネットに出ている情報をどう見るか?」という話題を通じて、世間の声と比べすぎない意識を持ったそうです。
マッチングアプリ婚は、急激に増えた新しい出会いの形です。
短い期間で距離を縮められる一方で、課題やリスクが見えにくくなることも。

だからこそ、お互いを深く理解し合うためのちょっとした工夫が、10年後のふたりの関係を大きく左右しますよ。