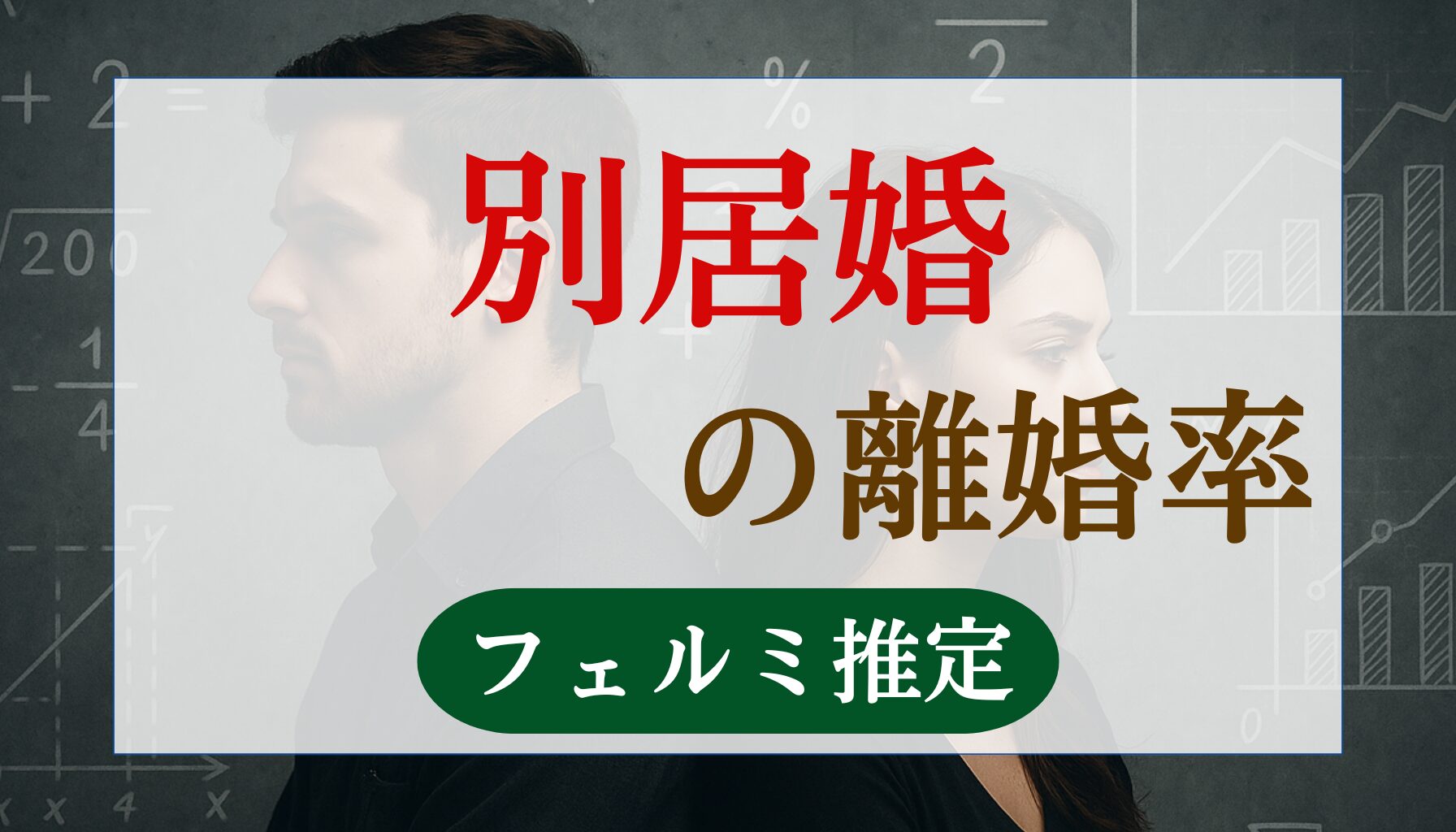別居婚の離婚率、実は0.43/1000人と推定されています。
これは全国の離婚件数の約29.2%。年離婚確率で見ると、なんと全国平均の約4.9倍なんです。
その根拠と背景を、以下で詳しく解説していきますね。
別居婚の離婚率をフェルミ推定で算出してみた【独自分析】
①別居婚とは?対象となる夫婦の定義
ここで言う「別居婚」とは、法律上は夫婦でありながら、長期間にわたり、自主的に別居しているカップルのことです。
単身赴任など、やむを得ない事情による別居に加えて、生活スタイルや夫婦間の事情から、あえて別々に暮らしているケースも含まれます。
②別居婚の割合はどれくらい?
別居婚に該当する夫婦の割合は、調査によってかなり幅があります。
たとえば、内閣府の2018年調査では「別居している夫婦は全体の2.1%」とされ、マイナビニュース(2024年)では「別居婚経験者は9.83%」との報告もあります。
今回は中間値である「6%」を採用し、別居婚の推定件数を算出してみます。
全国の既婚カップル数は2,735万組なので...
2,735万組 × 6% = 約164.1万組
つまり、日本国内にはおよそ約164.1万組の別居している夫婦がいると推定されます。
③仮定と統計から推定した年間離婚確率・件数は?
日本家族社会学会(2019年)の調査では、「別居婚になってから5年以内に離婚する確率は、同居婚の1.8倍」というデータがあります。
一般的な既婚カップルの10年間の離婚率を14.5%(年間離婚確率0.67%が10年間続いた場合の累積)と仮定すると、
別居婚層は 14.5% × 1.8 = 26.1% に達します。
これを1年あたりに換算し、累積離婚率から年率を求めると...
年率 r = 1 − (1 − 0.261)^(1/10) ≒ 2.99%
つまり、別居婚層のうち、1年で離婚する割合は約2.99%と推定されます。
該当カップル数164.1万組にこの確率をかけると…
164.1万組 × 2.99% ≒ 約49,046件
④別居婚の離婚率は全国平均の約4.5倍
推定によると、別居婚層の離婚は年間でおよそ49,046件。
これを日本の総人口(1億2,500万人)にあてはめて、人口あたりの離婚率を出してみましょう。
49,046 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.39/1000人
一方、全国全体の年間離婚率は1.52/1000人です(出典:厚生労働省『人口動態統計年計(2023年)』)。
つまり、別居婚層の離婚率は、全国平均のおよそ26%を占めているんですね。
また、年間49,046件という離婚件数は、1日あたりに換算すると…
49,046 ÷ 365日 ≒ 約134組/日。
これは、毎日134組の別居している夫婦が離婚しているということになるんです。
さらに、全国の既婚カップルの年間離婚確率は0.67%。
それに対して、別居婚層の離婚確率は2.99%です。

つまり、別居婚カップルは約4.5倍のリスクを抱えていることになります。
SNSと検索データから見えた別居婚離婚の実態
①SNSの声に見るリアルな葛藤と満足感
X(旧Twitter)で別居婚夫婦についての投稿を調査したところ、ポジティブな投稿が134件、ネガティブが83件、中立が49件。全体の約6割がポジティブでした。
「自分の時間を大切にできる」「心に余裕ができた」といった声が多く、精神的な自由や適度な距離感を肯定する意見が目立ちました。
ただし、「生活費が支払われない」「育児や移動の負担が片方に偏る」「孤独を感じる」といった、現実的な不満も少なくありません。
とくに「制度とのギャップ」や「経済的負担への不満」といった発言は、別居婚が必ずしも希望による選択とは限らないことを示しています。
こうした感情のばらつきが、離婚という判断に影響している可能性をふまえて、やや高めに1.15という補正係数を設定しました。
②Googleトレンドで読み解く注目度の急上昇
Googleの検索動向を見てみると、「別居婚」というキーワードは2023年ごろから急激に検索数が伸びています。
それ以前はほとんど検索されていなかったのに、ここ1年ほどは安定して高い注目を集めているんです。
背景には、テレビやニュースで取り上げられる機会が増えたことや、SNS上で「新しい夫婦のかたち」として広まったことがあると考えられます。
地域別で見ると、検索数が多いのは東京都を筆頭に、大阪府、神奈川県、京都府、福岡県など都市部が中心です。
理由として、都市圏では別居婚への認知が進んでいたり、交通の便が良く別々に住んでいても会いやすいことが、挙げられるかもしれません。
逆に、地方では検索ボリュームがかなり低く、そもそも「別居婚」という概念があまり知られていない可能性もありそうです。
こうした地域ごとの認知度のばらつきをふまえて、検索トレンドからの補正係数はやや低めに0.95と設定しました。
③SNS投稿と検索データを掛け合わせた真の離婚率
ここまでで設定したSNS補正係数1.15と、検索トレンド補正係数0.95を掛け合わせます。
1.15 × 0.95 = 1.0925
この補正係数をもとに、最初に推定した数値に反映していきます。
年間離婚件数:49,046件 × 1.0925 ≒ 53,563件
年間離婚確率:53,563 ÷ 1,641,000(別居婚カップル数) ≒ 3.27%/年
離婚率:53,563 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.43/1000人
そして、1日あたりに直すと…
53,563 ÷ 365 ≒ 約147組/日
つまり、毎日およそ147組の夫婦が、別居婚という形から離婚に至っているということですね。
また、この件数は全国の年間離婚件数183,808件のおよそ29.1%にあたります。

既婚層全体の離婚確率(0.67%)と比べると、別居婚層は約4.9倍の離婚リスクがあるんです。
別居婚夫婦の離婚率はどうなる?未来シナリオ予測
① 離婚件数が半減?社会と夫婦の歩み寄りが定着したポジティブな未来
まずは、制度の整備や別居婚への理解が進み、夫婦の対話や関わり方の工夫が定着していった未来を想像してみましょう。
この場合、現在の年次離婚確率3.27%から、毎年0.2ポイントずつ下がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
3.27% − (0.2 × 10) = 1.27%
この1.27%の離婚確率を、該当する別居婚層(164.1万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:164.1万組 × 1.27% ≒ 20,839件/年
離婚率:20,839 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.17/1000人
1日あたりで見れば、約57件/日もの離婚が発生する計算。
ここで注目したいのは、現在の数値(53,563件/年)から約32,724件もの離婚が削減できるということです。
つまり、1日あたり約90組の夫婦が離婚を回避できる計算になります。

「別居していても気持ちはそばにいる」...そんな関係なら、穏やかな未来もあり得るかもしれません。
② 離婚確率5.27%に上昇?悪化シナリオの行き着く先
一方で、制度の整備が進まず、夫婦のあいだに無関心やすれ違いが積み重なるような状況が続いたとしたらどうなるでしょうか。
このネガティブなシナリオでは、離婚確率が年に0.2ポイントずつ上がっていくと仮定します。
すると、10年後には…
3.27% + (0.2 × 10) = 5.27%
この5.27%の離婚確率を、同じく該当する別居婚層(164.1万組)に当てはめてみると、
年間離婚件数:164.1万組 × 5.27% ≒ 86,464件/年
離婚率:86,464 ÷ 125,000,000 × 1000 ≒ 0.69/1000人
1日あたりでは、約237件もの離婚が発生する計算です。
また、現在の補正後数値(53,563件/年)と比較すると、1年で約32,901件も多くなり、10年で32万件超の差が生じる可能性もあります。
そして、全国平均の離婚確率(0.67%)と比べると、5.27%は約7.9倍に相当します。

「物理的な距離そのまま心の距離になってしまう」...工夫しないとそんな未来が現実となってしまうんです。
③ 10年後の差と今できる対処策
ポジティブな未来(1.27%)とネガティブな未来(5.27%)を比べると、たった10年で4ポイント=約4.1倍もの離婚確率の差がつくことになります。
離婚率も、0.17/1000人 vs 0.69/1000人。
年間離婚件数では20,839件と86,464件という、なんと約65,625件もの違いが生まれます。
ネット上では、「結婚してる意味が分からなくなる」「子どもがいなければ続ける必要もないのでは」といった声も見られました。
一方で、「離れていても結婚を選んだのは操を立てるため」といった価値観の声もあり、そもそもの前提や意識に違いがあることもわかります。
こうしたギャップを埋めていくには、共通の目的や生活イメージを意識的にすり合わせることが大切です。
- 週に1回は話すなど、会うルールを作る
距離的な問題や忙しくて会えなくても、週に1回はビデオ通話をすると決めることで、お互いを大事に思う気持ちが伝わります。 - リモートで家族時間を作る
離れていても家庭の雰囲気を味わうためには、ビデオ通話での晩ご飯や映画鑑賞がおすすめ。別々の場所で同じことをしながら話すことで、心の距離が縮まります。 - スケジュールアプリで予定を共有する
浮気の心配まではないけど、相手の生活がまったく見えないのは不安になることも。カレンダーで予定を共有し、「今どこで何をしているか」がわかるだけでも安心できるものです。 - 育児や家事のサポートを受ける
どちらか一方が子育てや家事をすべて担うのは大変です。市のサポートや民間サービスを使ったりして、負担が偏らないようにする工夫をしましょう。
仕事の都合でやむを得ず別居しているのではなく、自分たちの希望で別居している夫婦は以下のような対策も必要です。
- なぜこの生活を選んだのかをふり返る
「どうして別居しているのか」を話し合い、お互いが納得することで、気持ちがずれないようにできます。 - うまくいかないという意見について話し合う
「別居婚は失敗しやすい」と言う人もいます。そんな声もあえて話題にして、「じゃあ私たちはどうする?」と考えることが、よい関係を作るチャンスになるかもしれません。 - 子どものために別居のままでいいのか考える
将来子どもが生まれたときには、ずっと別々に暮らすのは難しくなることもあります。子どもの成長や進学を考慮して、生活環境を再検討することが大切です。

一緒に住んでいなくても、心を近づける方法はきっとあるはずです。